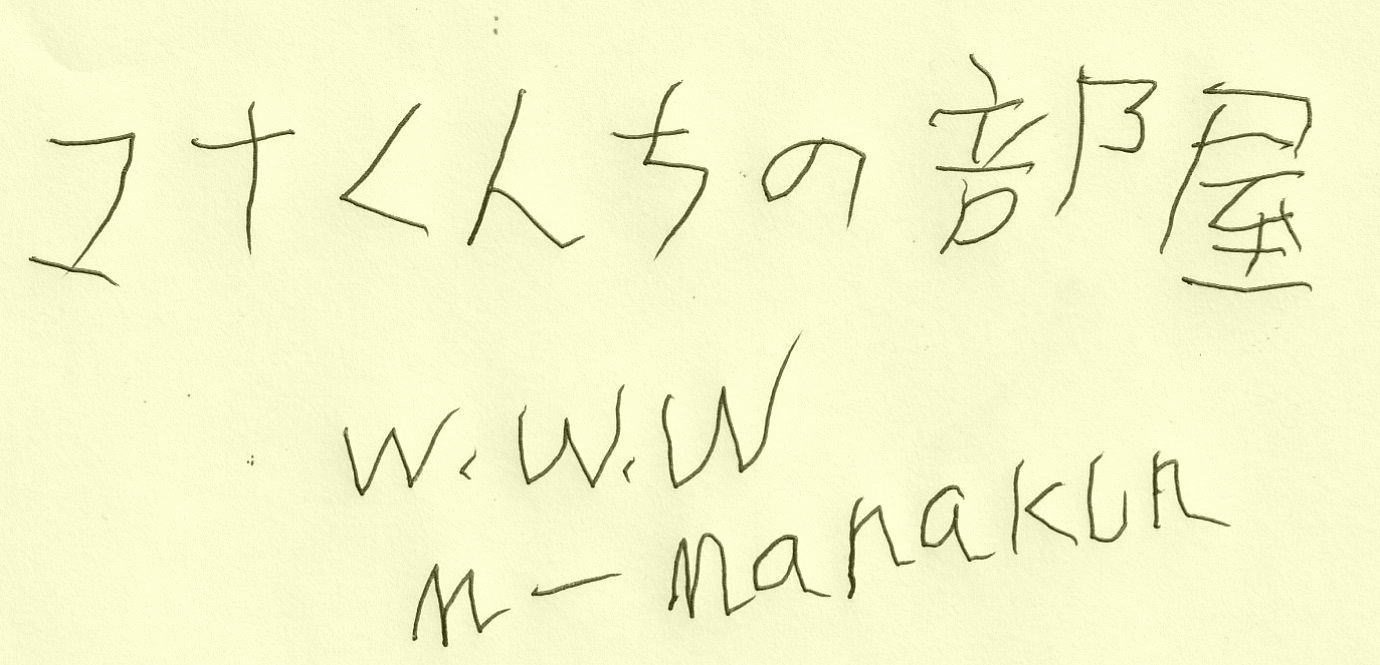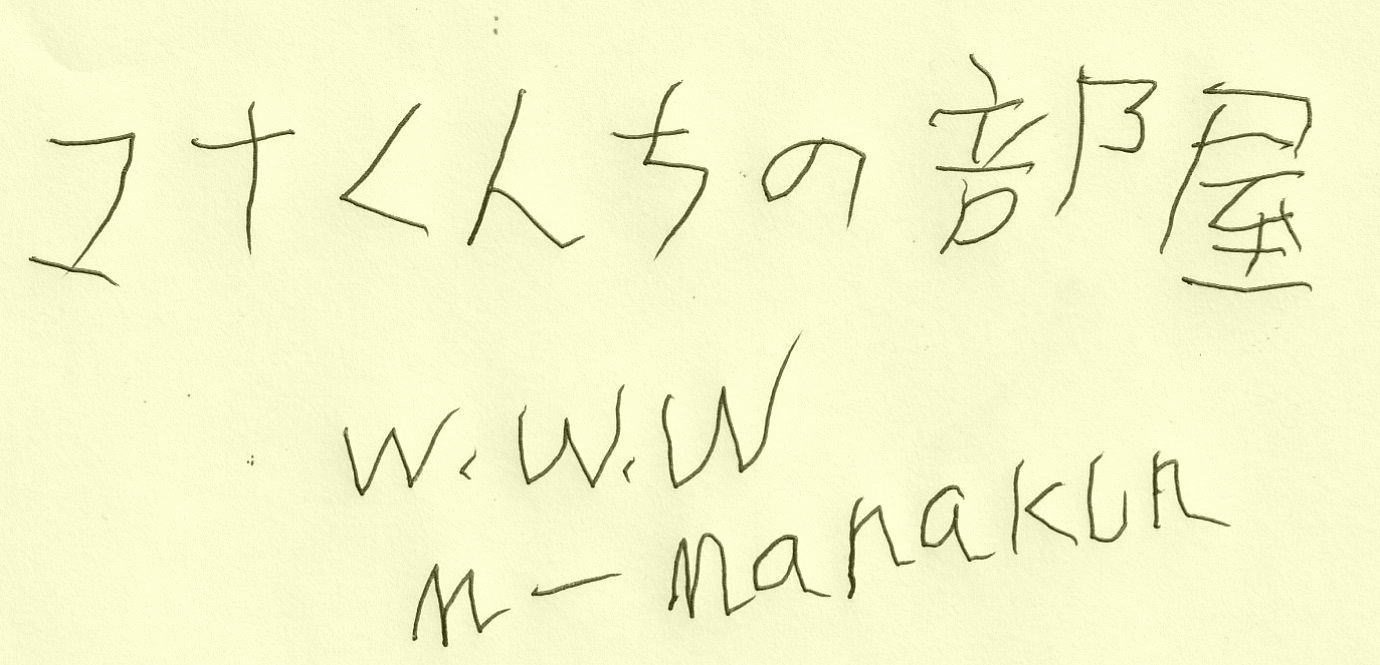|
北朝鮮による拉致被害者の一人、横田めぐみさんはいまどこにいるのか。生存と死亡説が交差する中で、全容解明には至っていない。拉致されてから今年 で47年。これまでに大物政治家も動く気配はあったものの、国という壁に閉されている。めぐみさんの家族は、どんな思いでいるのだろう。「元気でいますか。とにかく逢いたい・・・」。この一言を使うにしても、実際は言葉にも言い表せない、肉親にしか分からないものが秘められているに違いはあるまい。一方で、予知せぬ運命にさらさられ続ける大事件と、一家族の諦めない気持ちが人々の心を引き寄せている。 で47年。これまでに大物政治家も動く気配はあったものの、国という壁に閉されている。めぐみさんの家族は、どんな思いでいるのだろう。「元気でいますか。とにかく逢いたい・・・」。この一言を使うにしても、実際は言葉にも言い表せない、肉親にしか分からないものが秘められているに違いはあるまい。一方で、予知せぬ運命にさらさられ続ける大事件と、一家族の諦めない気持ちが人々の心を引き寄せている。
江戸時代に入るまでは大家族がほとんどであリ、生涯未婚のままの例も少なくなかったという。誰にも両親がいる。ここからスタート。大家族だと、祖父母・両親・本人・兄弟姉妹の構成となり、とても賑やか。自分たちの新しい家庭を築く小家族にも夢が育む。視線をずらせば、母子家庭・父子家庭・親里や施設で暮らす子ども・子どものいない家庭のほかに、養子縁組となった家族、学生や高齢者の一人暮らしもあり、少数集団生活はさまざまだ。
農家で長男として生まれた私は、後継ぎとしての責任感を持っていた。その結果が分かり、あと半年で満65歳となってしまう。先祖代々から受け継がれてきたものを終わらせるのは切ない。親亡き後を心配した両親も思いは同じだろう。いま自分ができるのは、残された時間(とき)を精一杯生きることに尽きる。支援者のCさんが退くことから、今年の初秋、介護支援専門員Aさんと話し合い、新たに支援団体にお願いをする運びとなっていた。それでも、何か割り切れない思いを抱きながら、年に 1回開催となる担当者ケア会議の日がやってくる。「これから先、支援をしてくださる・・・ありがたい。お互いに理解をし合うことが大切」。この一言を頭にたたきこみ、出席者の顔を見ていた。対して9名の耳が私の声に集中している。「(発声障害があるため)電話は苦手ですので、必要に応じてメールの返信をお願いします」。支援団体担当者さんの眼(まなこ)は私から逸れており、とても残念なことだった。 1回開催となる担当者ケア会議の日がやってくる。「これから先、支援をしてくださる・・・ありがたい。お互いに理解をし合うことが大切」。この一言を頭にたたきこみ、出席者の顔を見ていた。対して9名の耳が私の声に集中している。「(発声障害があるため)電話は苦手ですので、必要に応じてメールの返信をお願いします」。支援団体担当者さんの眼(まなこ)は私から逸れており、とても残念なことだった。
「【〇〇〇〇の会】というところがあります。資料を持って訪問します」。翌日、Aさんからメールがくる。先の担当者ケア会議に出席した、訪問看護師さんの紹介があったと聞く。別の支援団体組織だとも、ネット検索をしてみて分かった。一人暮らしの高齢者のお世話をしているらしい。身元保証、生活・入院・入所の各支援、万が一の葬儀段取りも受け入れるという。預けた支援金のチェック、そのほか法的な面では弁護士に依頼をするとしている。葬祭業の会社がバックにつく一般社団法人で、約40名余りの会員が支援を受けながら暮らす。「母と一緒に行った豊川稲荷へ、久しぶり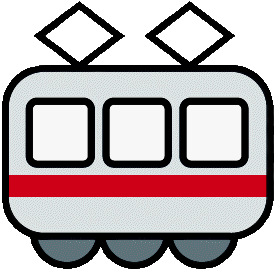 にお参りをしてきました」。支援スタッフと電車に乗り飯田線を南下。面影とともに新たな思い出ができたと、会の季刊誌で書き記す会員の声があった。年齢を重ね、いままでできていたことが思うにならなくなり諦めがちとなる。そんなとき、手を貸してくれる人がいたら、暗い気持ちがパッと晴れてくるもの・・・。「よしっ、前向きに考えていこう」。何だか、温かな気分になってきた。 にお参りをしてきました」。支援スタッフと電車に乗り飯田線を南下。面影とともに新たな思い出ができたと、会の季刊誌で書き記す会員の声があった。年齢を重ね、いままでできていたことが思うにならなくなり諦めがちとなる。そんなとき、手を貸してくれる人がいたら、暗い気持ちがパッと晴れてくるもの・・・。「よしっ、前向きに考えていこう」。何だか、温かな気分になってきた。
わが家へ少し早めに訪問したAさんと向き合っていると、会の相談員さん2人がお出ましとなる。40歳後半と思われる男性は眼鏡をしていて誠実そうな感じを覚えたし、もう一人は可愛らしく髪を後ろに束ね周りに明るさを広げる女性とみた。あいさつを交わすと、少し分厚い説明資料をもとに話が進んでいく。「ご説明をありがとうございます。2・3日ほどお時間をいただき、気持ちをお伝えします」。この日は建前上みたいな返事で終わらせたが、心は固まりつつあった。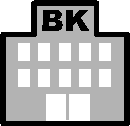 「どうしようかね。お金は大切でも、支援を受けなければ自宅では生活できない」。夜になると、一つの問いかけを御霊様の両親の位牌に尋ねた。「これからの生活のことだから、お前の好きなようにしなさい」。重たい一言は、寝ている間に枕元に届く。公的・個人年金などのほかに収入源はなく、財産でもある土地はただでも買ってはくれまい。公的な支援制度が充実するとよいけど、施設利用に傾く福祉社会のままだ。両親からの返事は、いまの社会を承知しての志に違いはない。支援団体に預けるお金は総計200万円で、契約したときから身元保証、財産管理、墓場まで保証がつく。何か変わったことがなければ、生活支援にかかわるお金が必要となり、追加金の請求がきそうだ。それを覚悟しての契約となる。「お金の支払いが難しくなったら、支援内容を見直していきましょう」。相談員男性はこう説明した。親切で人思いだと直感。約束通り、メールと口頭で相談員さんに心の内を告げる。順調に進んだと思う。 「どうしようかね。お金は大切でも、支援を受けなければ自宅では生活できない」。夜になると、一つの問いかけを御霊様の両親の位牌に尋ねた。「これからの生活のことだから、お前の好きなようにしなさい」。重たい一言は、寝ている間に枕元に届く。公的・個人年金などのほかに収入源はなく、財産でもある土地はただでも買ってはくれまい。公的な支援制度が充実するとよいけど、施設利用に傾く福祉社会のままだ。両親からの返事は、いまの社会を承知しての志に違いはない。支援団体に預けるお金は総計200万円で、契約したときから身元保証、財産管理、墓場まで保証がつく。何か変わったことがなければ、生活支援にかかわるお金が必要となり、追加金の請求がきそうだ。それを覚悟しての契約となる。「お金の支払いが難しくなったら、支援内容を見直していきましょう」。相談員男性はこう説明した。親切で人思いだと直感。約束通り、メールと口頭で相談員さんに心の内を告げる。順調に進んだと思う。
令和6年11月下旬。あっという間に支援団体と契約をする日がくる。相談員のお二人さんと同伴で、専属の弁護士さんの訪問を受けて初顔合わせとなった。名刺をこちらに差し出す黒髪の若々しい弁護士さんの第一印象は、その逆の想像を見事に崩されてしまう。ちらっと書類を見せてくれたので、身の上情報はある程度把握済みと分かる。契約書を交わすまでに、相談員さ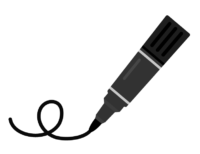 んが重要項目を読み上げ慎重な確認をしていった。認印を使い契約書類に印を押してもらおうとすると、弁護士さんがストップをかける。「スタンプ印ではダメです。実印でお願いします」。恐れ入ると同時に、これなら安心して任せられる組織であると心に置く。30分間くらいで契約を結ぶことができた。 んが重要項目を読み上げ慎重な確認をしていった。認印を使い契約書類に印を押してもらおうとすると、弁護士さんがストップをかける。「スタンプ印ではダメです。実印でお願いします」。恐れ入ると同時に、これなら安心して任せられる組織であると心に置く。30分間くらいで契約を結ぶことができた。
霜月いっぱいまでは、お試し期間とみなされるという相談員さんからのお話。すぐざま、生活支援をお願いする。お昼の食事の手配などを依頼したいときで、デイサービスに行かない日に支援を受ける形だ。1回の料金は2,200円。食事代金が1,000円の場合は、サービス代をプラスすると3,200円となる。支援金額の価値は理解できるけれど、支払い能力が心配の種。配達弁当をお試しに頼んだところ、配達無料で600円そこそこだ。デイサービスの昼ご飯や社協のお届け弁当と同じ感じで、おいしいとは言えなかった。私のリクエストに答える形式で支援者だったCさんが届けてくれた、おにぎりや総菜が口に合うよ うで頭から離れない。「お金を使い果たすか、食事で我慢をするか、これぞ勝負どころ・・・。恥じながら、思いっきりのよさを出してしまおう」。近所で支援奉仕活動をしていて、室内清掃、ゴミ出しをしてもらっている【お助け隊】のDさんに、すがるような思いを託す。間に入った相談員さんを通じ、自分の気持ちが確かに伝わった。「僕も協力はします」。家に顔を見せたCさんがニコニコして話してくれる。今後はお助け隊の一員で、特別な支援を任せない、そんな立場のCさんを温かく迎えることにしたい。 うで頭から離れない。「お金を使い果たすか、食事で我慢をするか、これぞ勝負どころ・・・。恥じながら、思いっきりのよさを出してしまおう」。近所で支援奉仕活動をしていて、室内清掃、ゴミ出しをしてもらっている【お助け隊】のDさんに、すがるような思いを託す。間に入った相談員さんを通じ、自分の気持ちが確かに伝わった。「僕も協力はします」。家に顔を見せたCさんがニコニコして話してくれる。今後はお助け隊の一員で、特別な支援を任せない、そんな立場のCさんを温かく迎えることにしたい。
公的支援の指揮者は介護支援専門員のAさん、民間支援では一般社団法人【〇〇〇〇の会】が身元保証の担当者、お隣さん同士のみなさんは【お助け隊】支援の力持ち。それぞれのポストが固まり閣組に至った。【宮脇を支えていく内閣】と、名付けようか。あぁぁ、お泊り介護施設の支援も忘れてはいけない。4閣僚の先生方、どうぞよろしくお願いします。
ウェブサイトを駆け巡った末に、いつの間にやらオペレータの年齢を覚えてしまったPC。つきまとうような広告サイト では、終活に関する情報が目立つ。【〇〇〇〇の会】と、同様な一般社団法人が多く存在しているとうかがえる。家族の形が変化してきた現在、【おひとりさま】の言葉 では、終活に関する情報が目立つ。【〇〇〇〇の会】と、同様な一般社団法人が多く存在しているとうかがえる。家族の形が変化してきた現在、【おひとりさま】の言葉 が定着しそうだ。調子弾みにデイサービスの責任者に一言申す。「僕はおひとりさまです」。意外な返事をもらう。「宮脇さんのお宅には、いろんな人 が定着しそうだ。調子弾みにデイサービスの責任者に一言申す。「僕はおひとりさまです」。意外な返事をもらう。「宮脇さんのお宅には、いろんな人 が出入りしていると思いますよ」。確かにそうだ。人に来てもらわないと、ほとんど一人では無理。結局、ひとりではない。先に記した4閣僚の先生方が家族なんだ。住む家があって、助けてもらえる家族がいて幸せである。横田めぐみさんも尊い家族に恵まれた。 が出入りしていると思いますよ」。確かにそうだ。人に来てもらわないと、ほとんど一人では無理。結局、ひとりではない。先に記した4閣僚の先生方が家族なんだ。住む家があって、助けてもらえる家族がいて幸せである。横田めぐみさんも尊い家族に恵まれた。
いままでの感謝を込めて、Cさんに贈りたい作文中編をここに書き記す。今回のラストはこれに決まり!。 梅雨入り宣言がまだない令和6年6月上旬、ショートスティ施設から介護タクシーを頼んで松本市へ出発する。この春以来「3カ月ぶりの小旅行となり・・・」と言いたいところ、そんなに物事はうまくはいかない。車内で私の横に座っている支援者のCさんは第一声を上げた。「こ れから寝るからね」。そう言うと、時間も要せずすぐに眠りつく。よほど疲れがあると見える。出かけるときからこんな調子では、何かしらけたように感じてしまう。だが、いまの時期、仕事の真最中の様子、何よりと思えば気も穏やかになる。中央自動車道・みどり湖パーキングエリアでトイレ休憩を済ませると、頭のスイッチがONに・・・。市内中心部に差しかかったら、急な渋滞に遭う。「そのところを右へ入って、今度の交差点を左折・・・」。A4サイズの用紙を広げ、素早く運転手に声をかける。10数年前、松本平でサラリーマンをしていたCさんは、目覚めたかのように領域を見せてくれた。偶然だとはしても、この人との出会いは、神からのものとも受け止めている。 れから寝るからね」。そう言うと、時間も要せずすぐに眠りつく。よほど疲れがあると見える。出かけるときからこんな調子では、何かしらけたように感じてしまう。だが、いまの時期、仕事の真最中の様子、何よりと思えば気も穏やかになる。中央自動車道・みどり湖パーキングエリアでトイレ休憩を済ませると、頭のスイッチがONに・・・。市内中心部に差しかかったら、急な渋滞に遭う。「そのところを右へ入って、今度の交差点を左折・・・」。A4サイズの用紙を広げ、素早く運転手に声をかける。10数年前、松本平でサラリーマンをしていたCさんは、目覚めたかのように領域を見せてくれた。偶然だとはしても、この人との出会いは、神からのものとも受け止めている。
 初代藩主・石川数正氏の松本城が近くある、信州大学医学部付属病院が行く先で、この辺りはキャンパス一色。大学本部をはじめ、一部を除く各学部が揃う。中でも医学部に関係した施設が目立つ。病院のほか、医学部キャンパス、専門図書館、医療研究のための学舎など建て並ぶ。体育館、野球場もあって、表現を変えれば学園広場みたい。2021年5月上旬、この病院へ入院する。なぜならば、脳性まひの二次障害である頚髄症の固定術を受けて、首の痛みをなくし、少しでも手足が動くようにしたかった。当時、リハビリテーションに力を入れる、健和会病院に入院中だったが、飯田市立病院からの紹介状を預かり、Cさんともう一人の支援者とともに、入院準備に備えた外来診察を受けに、2回ほど往復する。 初代藩主・石川数正氏の松本城が近くある、信州大学医学部付属病院が行く先で、この辺りはキャンパス一色。大学本部をはじめ、一部を除く各学部が揃う。中でも医学部に関係した施設が目立つ。病院のほか、医学部キャンパス、専門図書館、医療研究のための学舎など建て並ぶ。体育館、野球場もあって、表現を変えれば学園広場みたい。2021年5月上旬、この病院へ入院する。なぜならば、脳性まひの二次障害である頚髄症の固定術を受けて、首の痛みをなくし、少しでも手足が動くようにしたかった。当時、リハビリテーションに力を入れる、健和会病院に入院中だったが、飯田市立病院からの紹介状を預かり、Cさんともう一人の支援者とともに、入院準備に備えた外来診察を受けに、2回ほど往復する。
入院して3日目手術台に乗った。事前の説明文書だと、うつ伏せ状態から後頭部より胸椎付近までメスを入れ、首を丸見えにして固定するための金属を頚髄全体と頭の付け根、胸部先に縛りつけた模様である。これには8時間を要したが、集中治療室(ICU)から病棟へ移ったらすぐに普通食が出され驚く。が、手をつけられなかった。しばらくしたら、後頭部のところで左右方向に傷が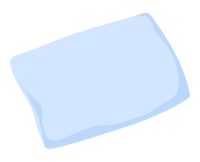 開き、再手術が必要となった。より頑丈な固定が先決となり、後頭部の先まで金属が埋め込まれた。頭のうしろ側に利き手を回すと、こぶ状の金具を3つ触れることができる。この金具、徐々に移動してしまい、3つのうち2つは頭の付け根まで下がってしまった。たとえば、機械浴用のストレッチャーに乗った際、ときによりこぶ状の金具に痛みを伴う。ストレッチャーの固い部分が金具にあたることで、頭部の神経に障ってしまうのであろうか。頭のあいだにクッションを入れると楽になるが、横向きになった場合、角度が高くなり過ぎ、首の金属に影響がありそうだ。 開き、再手術が必要となった。より頑丈な固定が先決となり、後頭部の先まで金属が埋め込まれた。頭のうしろ側に利き手を回すと、こぶ状の金具を3つ触れることができる。この金具、徐々に移動してしまい、3つのうち2つは頭の付け根まで下がってしまった。たとえば、機械浴用のストレッチャーに乗った際、ときによりこぶ状の金具に痛みを伴う。ストレッチャーの固い部分が金具にあたることで、頭部の神経に障ってしまうのであろうか。頭のあいだにクッションを入れると楽になるが、横向きになった場合、角度が高くなり過ぎ、首の金属に影響がありそうだ。
「冒険みたいなことをして困らせたね」。整形外科病棟の担当看護師さんから、こんな贈る言葉をもらった。院内にある、滝のように滑っていく温泉プールでおぼれてしまう。近くの神社まで集団外出をしたとき、車いすから落ちそうになって術後まもない首を痛めた。ベッドに置いてあった掛布団などを放り出し、大部屋には行きたくないと叫んだ。自分の行動以外では、ある日の夜、何者かが病室に入り、ベッドで横になっている私を横目に、壁に貼った参考資料やプリント写真を破り去っていく。また近くで、火炎瓶が投げつけられたような大きな音 がして、びっくり。病棟改修工事とは思えない、建物を壊すような衝撃音を日夜聞く。事実は分からないが、これら体験のなかったできごとは、学生運動(?)と無縁でないと感じたりもする。病院のホームページだと、自分が退院後に病棟などの改修・増設工事が行われているという。 がして、びっくり。病棟改修工事とは思えない、建物を壊すような衝撃音を日夜聞く。事実は分からないが、これら体験のなかったできごとは、学生運動(?)と無縁でないと感じたりもする。病院のホームページだと、自分が退院後に病棟などの改修・増設工事が行われているという。
担当医師は、整形外科に籍を置くリハビリテーション部助教授で、初診からいまの外来診察に至るまで、いつも私と向き合っている。術前・術後、これからの生活のことなど、笑みを浮かべて説明や話をしてくれた。再手術後は、すぐ病棟に戻ったけれど、高度集中治療室(HCU)へ移るように指示される。何日か経ってから担当医師に申し出る。「先生に相談があります。ここは暗くて外の景色も見えません。できれば一般病棟へ行きたいのです」。ベッドサイドに向かって精一杯声を絞り出す。「分かりました。今日中に戻る準備をし ます」。その一言がもらえて、うれしくて元気か出た。身のありさまはこうである。横目で見れば、首の裏側にカテールが取りつけられていて、そこから袋に血が溜まっていく。だから、24時間体制の看護が必要だったのであろう。休日以外は、ほかの先生方と一緒に回診しに足を運び、手術の際も担当医師の存在は光っていた。数人の看護師さんが口にする。「宮脇さん担当の先生は、飯田下伊那から患者を連れてきているみたいよ」。こんな噂には何か親近感を感じ得た。また「よくやったね」と、病院生活をねぎらうかけ声や、肺炎に要注意と警告する先生もいた。どれもよい方向へ解釈し、総括する担当医師を信頼していこうと思っている。 ます」。その一言がもらえて、うれしくて元気か出た。身のありさまはこうである。横目で見れば、首の裏側にカテールが取りつけられていて、そこから袋に血が溜まっていく。だから、24時間体制の看護が必要だったのであろう。休日以外は、ほかの先生方と一緒に回診しに足を運び、手術の際も担当医師の存在は光っていた。数人の看護師さんが口にする。「宮脇さん担当の先生は、飯田下伊那から患者を連れてきているみたいよ」。こんな噂には何か親近感を感じ得た。また「よくやったね」と、病院生活をねぎらうかけ声や、肺炎に要注意と警告する先生もいた。どれもよい方向へ解釈し、総括する担当医師を信頼していこうと思っている。
たまたま病院で、満61歳の誕生日を迎える。リハビリの先生や看護師さんらで特別チームが結成し、寄せ書きや会食にケーキが配られた。「宮脇さんの笑顔がいいねぇ~」。この言葉文字が寄せ書きの中央に配置され、まわりにひとり一人の思いがこもった一言が書き刻まれる。自宅寝室の壁には、A3サイズの寄せ書きがいまも色あせずに、私を励まし続ける日々だ。ベッドは一日の疲れを取り除いて、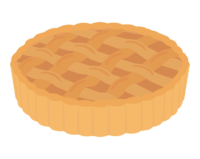 翌日の活力源とする大切な目的を持つ。しかし、高齢者または重い病気を患うと(ベッドは)日夜を過ごす居場所ともなる。「可能な限り活動範囲を広げていきたい」。2度の手術を経験して、ベッドから抜け出そうと必死になっていく。いまの暮らしは、医療・介護、支援者の理解と協力からできていて、ただただ感謝のみである。 翌日の活力源とする大切な目的を持つ。しかし、高齢者または重い病気を患うと(ベッドは)日夜を過ごす居場所ともなる。「可能な限り活動範囲を広げていきたい」。2度の手術を経験して、ベッドから抜け出そうと必死になっていく。いまの暮らしは、医療・介護、支援者の理解と協力からできていて、ただただ感謝のみである。
Cさんはこの5月の終わりに1枚の文書を、私と介護支援専門員のAさんにも渡す。3月に封切りをした引退話だ。財産の処分等を含め、自身が早く身の振り方を決めなければいけないかと思い、とてもあせってしまう。だが、ときが経つにつれ、ほんの少し受け止めに変化が生じはじめる。(私に)これから先を考えていく機会をつくり、Cさんら支援者が身を引くといった構図となる。「いままで、学さんとのかかわりを一言でいえば『責任感』での関わりでした。自分自身の性格を客観的にみると『世話好き』なのかな。よく言えば『世話好き』。悪く見れば『仕切り魔』。段取り好きで、押し切りタイプ。だから、何も縁もない学さんとのお付き合いができたのだと思っています。来年の3月で、すべてのお手伝いを辞めさせていただきたい。その前に、後任が現れるとしたら、いつもでも卒業させてください。(Cさんの文 書から核心点を抜粋)」。振り返ると、普通とは思えない《仮面の忍者》みたいな感じがする。このありさまは、母が他界してから見えてきた。ときして厳しい態度で臨む親心があれば、穏やか笑みを浮かべ優しさにあふれる瞬間、無表情さを振る舞う顔など、その場において心豊かな人である。仕事でヤギの飼育に専念しているところからも、確かに世話好きだ。遠い親類にはあたるとしても、血のつながらない同士、区切りづけどきとしたい。 書から核心点を抜粋)」。振り返ると、普通とは思えない《仮面の忍者》みたいな感じがする。このありさまは、母が他界してから見えてきた。ときして厳しい態度で臨む親心があれば、穏やか笑みを浮かべ優しさにあふれる瞬間、無表情さを振る舞う顔など、その場において心豊かな人である。仕事でヤギの飼育に専念しているところからも、確かに世話好きだ。遠い親類にはあたるとしても、血のつながらない同士、区切りづけどきとしたい。
外来診察を終え帰りの道中、Cさんと一緒にパーキングエリアで昼食を摂り帰路に就く前、私はつぶやく。「あと何回、Cさんと松本へ行けるかな」。隣を向くと微かなうなずきがあり、切ない思いが込み上げてきた。2度の手術に、一人で来院、面会、待合室にいてくれたCさん。世話好きだからで きるというものではあるまい。いや、家族だった。自分ができる恩返しは、Cさんの頭から私を思い浮かばせない、新たな暮らしに重視してもらうに尽きる。これからも、自分のために一生懸命生きていくだけだ。Cさん、ありがとうございました。 きるというものではあるまい。いや、家族だった。自分ができる恩返しは、Cさんの頭から私を思い浮かばせない、新たな暮らしに重視してもらうに尽きる。これからも、自分のために一生懸命生きていくだけだ。Cさん、ありがとうございました。
2024/12/10
|