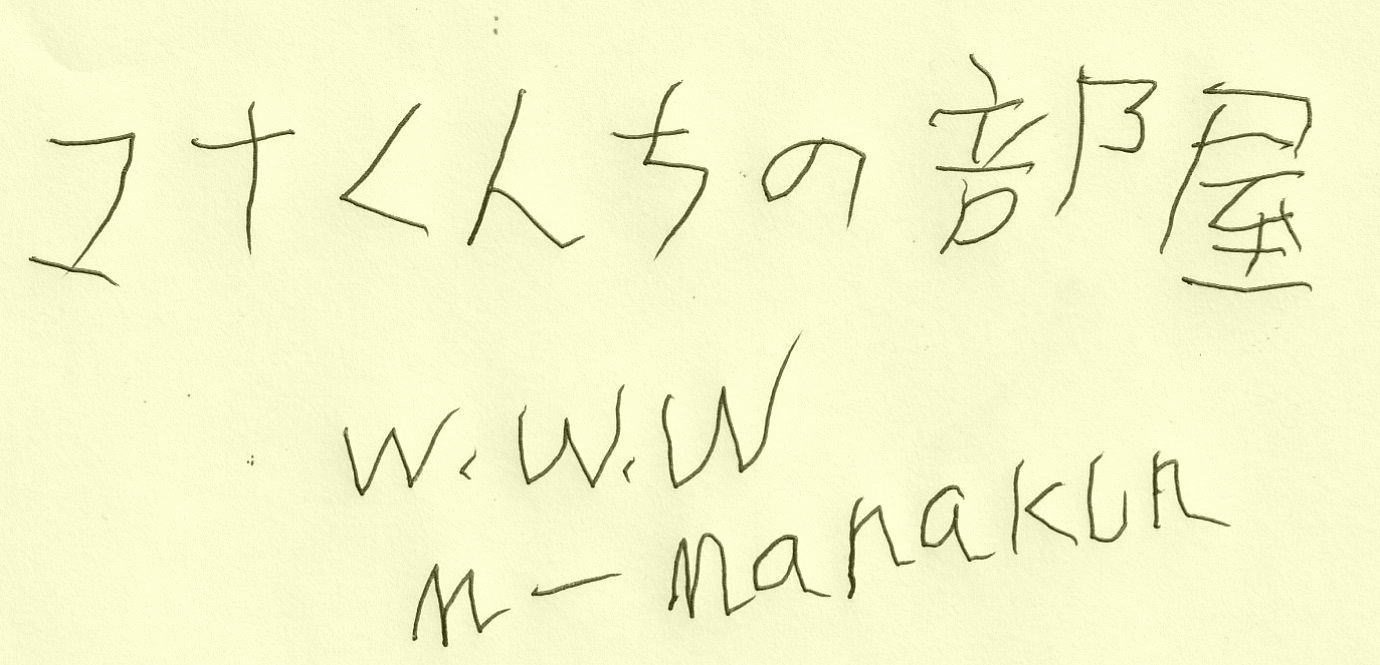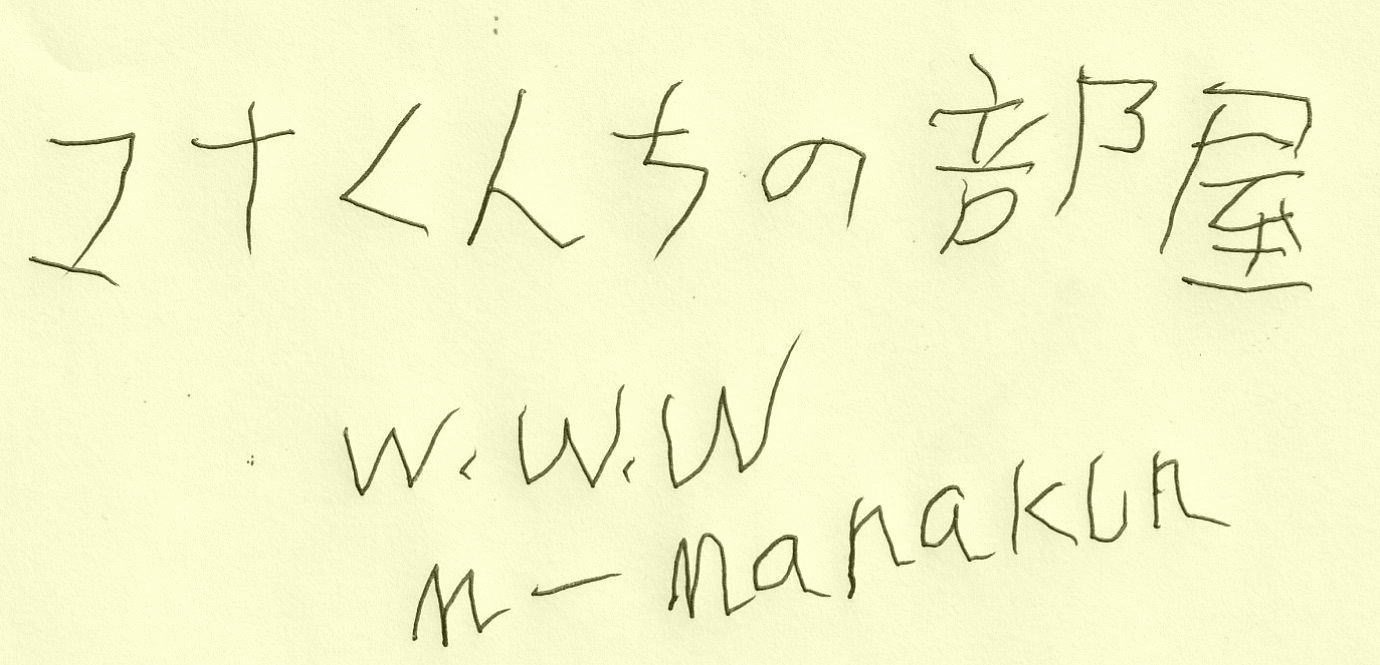|
昭和35年生まれだとすると、今年の誕生日をもって満65歳を迎える。私もこの6月で、前期高齢者の仲間入りをした。そんな思いを抱くと、自ら年老いを認めてしまう。健康体なら、まだまだ月給取り、パート勤めもいれば会社の経営者も多い。これだけは年齢を計り替わりにはできないし、個人それぞれの人生とみるべきであろう。 けれども法の下では、一定の線引きをしなければならない。一番身近に見えるなら、基礎年金支給開始年か。二番手は聞き慣れない一つ、第1号被保険者の言葉が浮かぶ。40歳から保険料を納める、介護保険サービスの線引きだ。役所(役場)で要介護認定を受けない場合は、この保証制度は万が一のお守りとなりそう。またそうでないと、公的サービスは成り立たなくなるかもしれない。三番手は「65歳の壁」。これは一体何なのか。 けれども法の下では、一定の線引きをしなければならない。一番身近に見えるなら、基礎年金支給開始年か。二番手は聞き慣れない一つ、第1号被保険者の言葉が浮かぶ。40歳から保険料を納める、介護保険サービスの線引きだ。役所(役場)で要介護認定を受けない場合は、この保証制度は万が一のお守りとなりそう。またそうでないと、公的サービスは成り立たなくなるかもしれない。三番手は「65歳の壁」。これは一体何なのか。
脳性まひ後遺症を背負う千葉県内の男性は、役所からの指導を拒み、満65歳を過ぎても要介護認定申請を出さなかった。これを受けて、すべての公的サービスから見放されてしまう。男性は65歳に至る前は、どのようにしてヘルパーさん(訪問介護)を頼んでいたのであろうか。子どもや障害を持つ人の暮らしを支える目的から法定化された、その名称は障害者総合支援法と児童福祉法基本法。この2つの法の下で定められた、障害福祉サービスがあり、居宅介護から介護職員の訪問を受けることができるほか、重度訪問介護・生活介護(デイサービス)・短期入所(ショートステイ)、行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援などが、(介護保険サービスに対し)固有のサービスとして追加となる。一方で、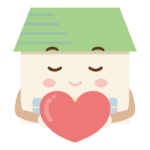 主として前期高齢者から対象となるのが介護保険サービス。介護保険法での決まりだ。ヘルパーさん利用は訪問介護と言い、デイサービスが通所介護で、ショートスティ(短期入所)と続く。なんだか並ぶ名前が(比較サービスとは)紛らわしく思うが、メインの3本立てで後期高齢者までの暮らしを支えていくというもの。 主として前期高齢者から対象となるのが介護保険サービス。介護保険法での決まりだ。ヘルパーさん利用は訪問介護と言い、デイサービスが通所介護で、ショートスティ(短期入所)と続く。なんだか並ぶ名前が(比較サービスとは)紛らわしく思うが、メインの3本立てで後期高齢者までの暮らしを支えていくというもの。
どうして男性は、介護保険サービスへの抵抗があったのだろう。利用者が負担する仕組みが、法の建前から違いが生じる。個人の所得に応じて、その額が計算され納める義務を負うが、非課税の場合でも月々1割を支払わなければならない。だが、同じ環境下にあっても比較するサービスだと、男性は負担額ゼロとなる。障害基礎年金だけの暮らしでも、介護保険サービスは一律1割がかか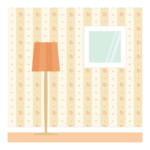 ってしまう。それなら、誰でも払わない方を選びたい。結果として65歳に達するとなぜ、無料ではなく有料となるのか。サービス趣旨の違いは公平といってよいのだろうか。率直な疑問が同じ境遇の仲間の間で広がり、新たな言葉が生まれた。出だしに書いた「65歳の壁」である。法廷へ疑問を投げかけた男性は、76歳になったいまもはっきりとした答えが見つからずに過ごす。決まりがあっても、ことがスムーズに進むばかりでもなさそう。 ってしまう。それなら、誰でも払わない方を選びたい。結果として65歳に達するとなぜ、無料ではなく有料となるのか。サービス趣旨の違いは公平といってよいのだろうか。率直な疑問が同じ境遇の仲間の間で広がり、新たな言葉が生まれた。出だしに書いた「65歳の壁」である。法廷へ疑問を投げかけた男性は、76歳になったいまもはっきりとした答えが見つからずに過ごす。決まりがあっても、ことがスムーズに進むばかりでもなさそう。
満65歳まであと3年となったとき、私は介護保険法で定められた16の特定疾病(第2号被保険者)の一つに該当すると、入院中に告げられた。つまり、介護保険サービスを使えそうだとのお伺いがきた。さらに追加言葉を確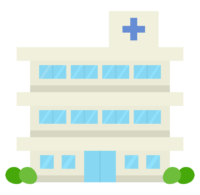 かに聞く。「3年間待てば、サービス移行後も負担金が軽減されますよ」。その期間はどのくらいかは忘れたけども、1割負担ではないとの覚えがある。現在、ネット検索を試みるが、追加言葉に当てはまる情報は見つかってはいない。「入院継続ではなく、ヘルパーさんにお願いをする自宅生活に戻していきたい」。この思いが強く当時、私にはときを待とうとする自信がなかった。 かに聞く。「3年間待てば、サービス移行後も負担金が軽減されますよ」。その期間はどのくらいかは忘れたけども、1割負担ではないとの覚えがある。現在、ネット検索を試みるが、追加言葉に当てはまる情報は見つかってはいない。「入院継続ではなく、ヘルパーさんにお願いをする自宅生活に戻していきたい」。この思いが強く当時、私にはときを待とうとする自信がなかった。
国民すべてが介護保険料を納めはじめる40歳から65歳の誕生前日までを第2号被保険者といい、以降の年齢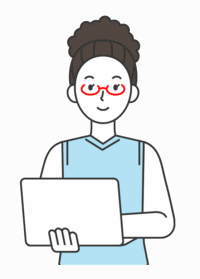 は第1号被保険者となる。退院に向け、要介護認定申請、介護支援専門員(ケアマネジャー)選出、通所介護をどこの施設にするかなど、一つ一つステップを踏む。私は特定疾病に入る脊柱管狭窄症で、いわゆる背骨プラス首曲がり。自分でも一瞬、背筋が寒くなってしまう老化現象だ。こんな身体だから要介護4となり、介護保険サービス利用をスタートさせた。が、もともと早く使いたいという願望があり、ついにきたなとつぶやく。訪問介護事業所長さんは20年ほど前からの知り合いであり、ケアマネさんならAさんだと決め込んでいた。 は第1号被保険者となる。退院に向け、要介護認定申請、介護支援専門員(ケアマネジャー)選出、通所介護をどこの施設にするかなど、一つ一つステップを踏む。私は特定疾病に入る脊柱管狭窄症で、いわゆる背骨プラス首曲がり。自分でも一瞬、背筋が寒くなってしまう老化現象だ。こんな身体だから要介護4となり、介護保険サービス利用をスタートさせた。が、もともと早く使いたいという願望があり、ついにきたなとつぶやく。訪問介護事業所長さんは20年ほど前からの知り合いであり、ケアマネさんならAさんだと決め込んでいた。
入院3か月後の退院となったものの、最初の数カ月ほどは月々10日間の自宅生活で、残りが療養病棟ショートスティの繰り返し。病院過保護のようなものであり、ケアマネAさんの色合いは薄めであった。おそらくこれでは、病院から離れられない。「もう(病院生活は)懲り懲りです」。一方で思いやりも感じた。「障害を抱えての暮らしは大変だろうから、できるだけ病院が支えたい」。私と病院の気持ちが、確かにAさんへ投げかける言葉となった。きっかけづくりができ、はじめてAさんの知的な手段で、高齢者施設での短期入所をはじめる。何も知らなかった施設暮らしは、自分以外の利用者も介護が必要な場合がほとんどで、1970年代ころ多くのお年寄りが出かけた、農協主催の温泉保養とは別世界とも思えた。高齢の祖母、両親の年代に入ると、介護保険法の執行によって介護がいらなければ、いままでと同様に元気で過ごす環境が整う。末期がんで苦しんだ父は、通所介護施設はじめヘルパー利用さえ も拒んだ。それだけ負担が母の肩にかかったけれど、精いっぱいの手助けはまさに夫婦愛を見させてもらう機会に・・・。「私は絶対、介護保険サービスは使わない。学(お前)はいつもでも、要介護認定申請をしなさい」。こう聞かされ、両親の愛し合った証に触れる思いがした。 も拒んだ。それだけ負担が母の肩にかかったけれど、精いっぱいの手助けはまさに夫婦愛を見させてもらう機会に・・・。「私は絶対、介護保険サービスは使わない。学(お前)はいつもでも、要介護認定申請をしなさい」。こう聞かされ、両親の愛し合った証に触れる思いがした。
つい最近、後期高齢者の仲間入り目前という男性ヘルパーさんに、私は口を切る。「いまの自分の気持ちは、○○さんにケアをしてもらえてありがたく思っています。これからもお身体に留意されて、私の介護をしにきてください」。じっと聞き入るヘルパーさんに話し続けた。「個人的な思いとなりますが、できるなら介護のサービスは利用しない方がいいですね。自分も 一人で暮らせる状態なら、一生利用しないで生きていきたいです」と・・・。どう見ても、正反対の気持ちに変わってしまっている。両親と同じような思考を抱くありさまに、不思議でならなかった。自然ななりゆきとはいえ、やはりそれではいけない。自分が生活をしていく上では、なくしてはならない介護保険サービスと位置づけていこう。 一人で暮らせる状態なら、一生利用しないで生きていきたいです」と・・・。どう見ても、正反対の気持ちに変わってしまっている。両親と同じような思考を抱くありさまに、不思議でならなかった。自然ななりゆきとはいえ、やはりそれではいけない。自分が生活をしていく上では、なくしてはならない介護保険サービスと位置づけていこう。
交流サイト(SNS)へ投稿をしてみた。「さっそくですが、みなさんにお尋ねいたします。公的サービスには、障害福祉サービスや介護保険サービスがあり、ケアが必要なときにとても便利だと思います。日常の生活の中で公的サービスを利用されていますか。いや、それとも自立、施設入所あるいは入院継続を希望されているのでしょうか。できたら、あなたのありままの生き方を教えていただけませんでしょうか。(脳性まひ後遺症の私は、介護保険サービスをマストに障害福祉サービスも併用する形で、今後も自宅生活を続けていきたいと思っています)」。人によって考えはまちまちだし、回答者が限られており、適切な情報は少なかった。施設で暮らす一人の返答者は、近い将来に グループホームへの仲間入りを希望。うつ病、摂食障害がある人の場合、公的サービスよりも医療保険から訪問看護での指導を受けていきたいとの回答を得る。寝たきりに起因する障害悪化の防止を考え、通所介護、週2日の障害者就労に通い、世間の刺激を感じられるよう努めているという、脳出血による高次脳機能障害および片麻痺の男性は、公的サービスを評価していた。真剣にこれからのことを模索し、よい方向へと歩む姿勢は回答者全員の共通点である。 グループホームへの仲間入りを希望。うつ病、摂食障害がある人の場合、公的サービスよりも医療保険から訪問看護での指導を受けていきたいとの回答を得る。寝たきりに起因する障害悪化の防止を考え、通所介護、週2日の障害者就労に通い、世間の刺激を感じられるよう努めているという、脳出血による高次脳機能障害および片麻痺の男性は、公的サービスを評価していた。真剣にこれからのことを模索し、よい方向へと歩む姿勢は回答者全員の共通点である。
訴訟を起こしている千葉の男性は、よりよい暮らしを求めていることが、理由付けとなりそうだ。不可欠な法の見直しや、財政を考慮する情報交換が解決となるのではないだろうか。住民票がある自治体が被告 なので、話し合いから和解へ進むのがベストとなろう。ざっと、自分の経過を振り返ったとき、公的サービスの仕組みに批判意識を強めるばかりでなく、ケアマネジャーと相談を重ね、上手な利用の心がけも必要かなと思う。いまの法律をよく理解し、自分が納得のいく形の公的サービスを利用したいものである。 なので、話し合いから和解へ進むのがベストとなろう。ざっと、自分の経過を振り返ったとき、公的サービスの仕組みに批判意識を強めるばかりでなく、ケアマネジャーと相談を重ね、上手な利用の心がけも必要かなと思う。いまの法律をよく理解し、自分が納得のいく形の公的サービスを利用したいものである。
2025/08/18
|