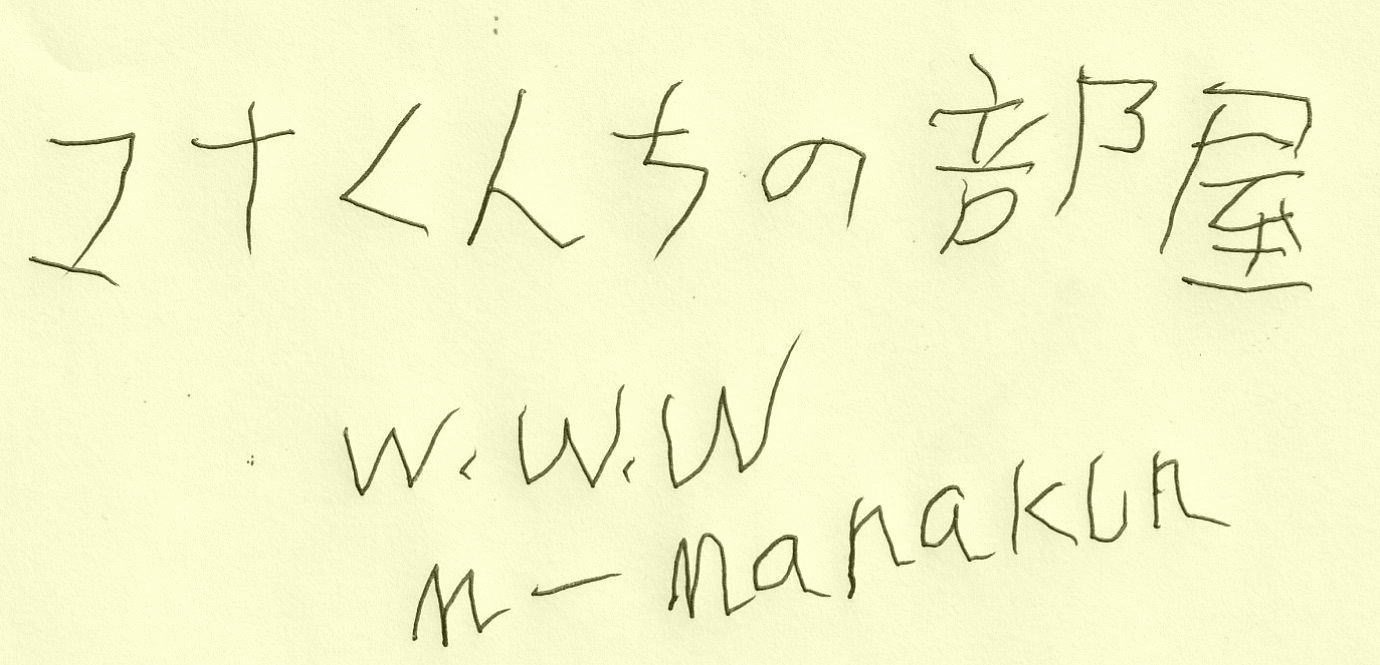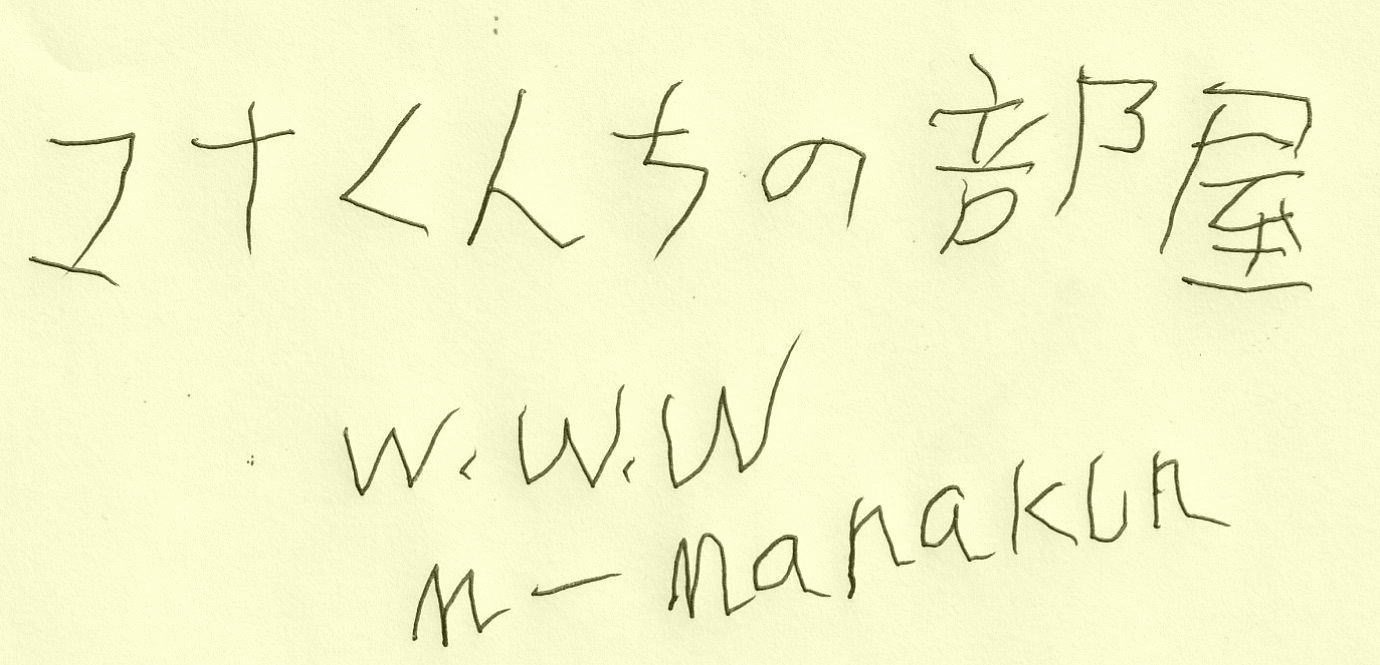|
近年、食べ物の中でもなかなか口には入らない秋のベストワンは、新生さんまあるいは松茸ではないだろうか。昨年は凶作に終わったものの一転、お盆前後で降った恵みの雨が豊作とつながった。「まつたけ観光」という名称が染みついた隣村の意気込みはたっぷりな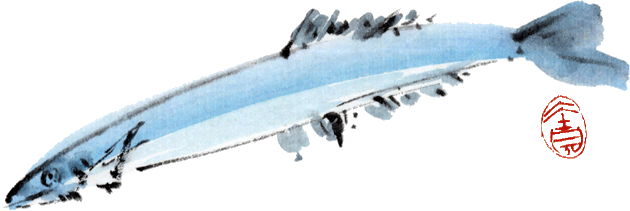 様子で、村内の小中学校で「まつたけ給食」があり子どもたちを喜ばせたとか・・・。売り込みもまずまずと思うが、まわりの自治体は現実味に帯びた感がうかがえる。 様子で、村内の小中学校で「まつたけ給食」があり子どもたちを喜ばせたとか・・・。売り込みもまずまずと思うが、まわりの自治体は現実味に帯びた感がうかがえる。
関係しない話題に移りたい。「障害を隠さない」。未熟児だった私は、生後間もなく酸素不足に陥り、発達途上の脳に重いダメージを受けた。医学用語なら「脳性まひ後遺症」となる。「脳血管などの疾患」とは別物。当時はまだ【新生児集中治療管理室(NICU)】や【回復治療室(GCU)】が公立病院にしかなく、本人の生命力に委ねざるを得ぬ状況下だった。例えば、なんて思ってみたところが、手足が自由に動く、正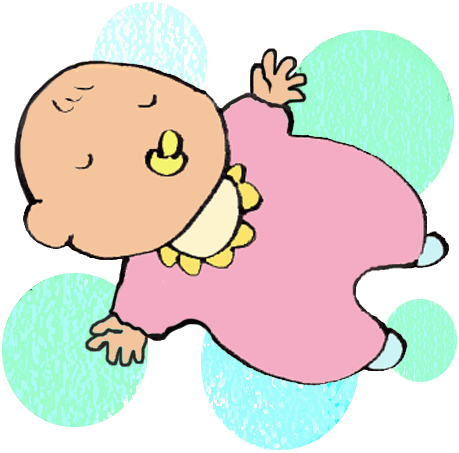 常な発声ができようもあるまい。授けられた障害と自らがどう向き合い、前向きにとらえていくかが希望の光となろう。思考を変えることなく、60年以上の歳月が経つ。両親をはじめ家族にも、同じ思いが沁み込み全員一心の精神があった。障害は自分そのもので、決して不幸の言葉は思い浮かばない。 常な発声ができようもあるまい。授けられた障害と自らがどう向き合い、前向きにとらえていくかが希望の光となろう。思考を変えることなく、60年以上の歳月が経つ。両親をはじめ家族にも、同じ思いが沁み込み全員一心の精神があった。障害は自分そのもので、決して不幸の言葉は思い浮かばない。
「隠さずにつき合っていく」。ほかの仲間の共通点を探ってみたい。1986年に放送されたNHK特集「のぞみ5歳〜手さぐりの子育て日記〜」が、令和6年4月12日「時をかけるテレビ」という番組名で、再び画面に登場する。目が不自由な男女が両親の反対を押し切り、家庭を築いていくドキュメンタリー。その夫婦の間に生まれた女の子が、両親と苦難に当面しながら明るく暮らす様子を伝えている。笑みを浮かべてお父さんは話す。「私たち夫婦には、停電したってすぐには分からない。けれど、のぞみには何でも見える。一緒に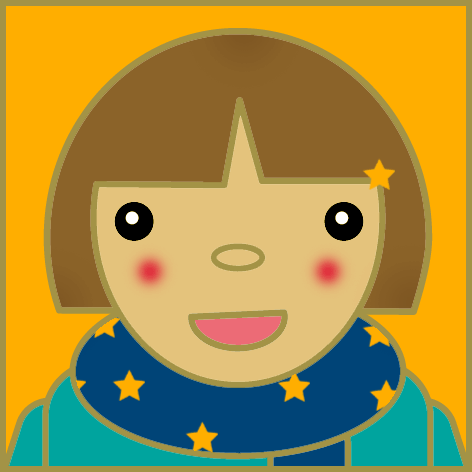 生活をする中で、目が見えるような思いがします」。わがままを言って困らせると、ひとりの親に返って叱り泣き止むのを待つ。何度も同じことを繰り返し、まもなくすると、お母さんの外出で道案内を買って出たのぞみちゃん。「この子が授かる前は、自分同様、目に障害を持つ赤ちゃんが生まれたら、どうしようかって考えてみたこともありました」。お母さんは、遺伝はないと信じてわが子を産み、一人前の人間に育てたいという意志が強かった。お父さんとお母さんの深い愛情を受けて、近くの幼稚園へ通うまでになった。チャレンジド同士で結婚するケースが多いほかに、健康な身でも何らかの障害を持つ人とカップルになることも・・・。一緒に暮らす2人が社会的な心のハンディ(弱点)を乗り越えながら、家庭づくりの機会が増えるとよいと思う。そうした姿から、より広く理解の輪が大きくなるのではないだろうか。一人の女の子の成長記録は、多くの人から感動メッセージがNHKに舞い込んだという。「障害は関係ないと思います。両親は苦労の連続だったと、自分も母になってみて痛感しました」。いま40代ののぞみさんの胸には、感謝の言葉しかない。お母さんが最後に語った。「とにかく諦めないでほしい。よいときがくると信じて・・・」。すべての人に共通するホットな伝言である。 生活をする中で、目が見えるような思いがします」。わがままを言って困らせると、ひとりの親に返って叱り泣き止むのを待つ。何度も同じことを繰り返し、まもなくすると、お母さんの外出で道案内を買って出たのぞみちゃん。「この子が授かる前は、自分同様、目に障害を持つ赤ちゃんが生まれたら、どうしようかって考えてみたこともありました」。お母さんは、遺伝はないと信じてわが子を産み、一人前の人間に育てたいという意志が強かった。お父さんとお母さんの深い愛情を受けて、近くの幼稚園へ通うまでになった。チャレンジド同士で結婚するケースが多いほかに、健康な身でも何らかの障害を持つ人とカップルになることも・・・。一緒に暮らす2人が社会的な心のハンディ(弱点)を乗り越えながら、家庭づくりの機会が増えるとよいと思う。そうした姿から、より広く理解の輪が大きくなるのではないだろうか。一人の女の子の成長記録は、多くの人から感動メッセージがNHKに舞い込んだという。「障害は関係ないと思います。両親は苦労の連続だったと、自分も母になってみて痛感しました」。いま40代ののぞみさんの胸には、感謝の言葉しかない。お母さんが最後に語った。「とにかく諦めないでほしい。よいときがくると信じて・・・」。すべての人に共通するホットな伝言である。
「声取り戻す場なくさないで」。新年度がはじまって4月6日、地方紙の投稿欄に躍っていた一つの見出しは、喉のがんで声帯を摘出した高齢男性の心の声だ。「同じ病気を患ったみなさんで構成する団体に所属し活動しています。組織の目的は失った声を取り戻すことで、長野県内5か所の病院で一室を借りて発声教室が開設されています」。「声を取り戻す」とは、どういうことなのか一瞬、考えてしまいがちだ。食道のヒダ(襞)を振動させる発声法、喉に電気式人工喉頭機をあて、ブザー音が声に代わる方法の2例がある。80歳の投稿者は20年前に入会すると、いまは指導員で松本の教室に通い、後輩とともに発声訓練に励んでいるという。しかし、一時は県内に200人いた会員が現在、約半分以下に減少されてしまう。このような状況下では、各教室の存続が危ぶまれるほか、一堂に会しての対面訓練の機会を見直すことが必要になると心配する。会員の高齢化、医療進歩、病気予防啓発(喫煙率の低下)などが、その原因につながるらしい。いま亡き母は、タバコを吸ったことはないと話すが、咽頭がんになってしまい術後、男性会員の中に混じり活動をする。ほとんどが奥様同伴でまわりの雰囲気を壊さず、発声トレーニングとお互いの親睦を大切にしていた。交通手段には駒ケ根市の会員に依頼をして、クルマで片道15分ほどかか る飯田教室へ月に2回通う。重い心臓病の奥さんと2人暮らしのこの会員を、母は大事にする。教室単位の行事に出かけるときは、私も同行を許された。新年会・忘年会のほか、毎年5月に場所を変えながら、阿智園原、県南天龍、妻籠へも行く。すべては、教室のまとめ役のおかげである。今回投稿を目にして、インターネットで検索したら、覚えがある団体名にヒットした。「当時、飯田教室の代表を務めていた方は、3年前に退かれました。声を失う方が毎年一定数おられるので、私たちの活動を途絶えさせるわけにはいきません。これからも、会員のみなさん一丸となってがんばっていきたいと思います」。第一に母がお世話になったことを伝えようと思い、見つかったホームページに記載があったメールアドレスへ送信した。メールを送ってくれた人は、団体の会計係を担当しているそうで、先の投稿者の後任だという。近年では、創立50周年の記念式典をはじめ、第74回保健文化賞の受賞(第一生命主催)、長野県知事から社会福祉功労団体として表彰されている。「声を取り戻す」。声帯があれば何でもない、大きな試練に立ち向かうみなさんに、いままでの感謝と今後の活躍を心から祈念したい。いつ誰かが、この団体に入会するか分からないことを、世間にも周知してもらうとよいと思う。『長野県信鈴会』・・・団体名称である。 る飯田教室へ月に2回通う。重い心臓病の奥さんと2人暮らしのこの会員を、母は大事にする。教室単位の行事に出かけるときは、私も同行を許された。新年会・忘年会のほか、毎年5月に場所を変えながら、阿智園原、県南天龍、妻籠へも行く。すべては、教室のまとめ役のおかげである。今回投稿を目にして、インターネットで検索したら、覚えがある団体名にヒットした。「当時、飯田教室の代表を務めていた方は、3年前に退かれました。声を失う方が毎年一定数おられるので、私たちの活動を途絶えさせるわけにはいきません。これからも、会員のみなさん一丸となってがんばっていきたいと思います」。第一に母がお世話になったことを伝えようと思い、見つかったホームページに記載があったメールアドレスへ送信した。メールを送ってくれた人は、団体の会計係を担当しているそうで、先の投稿者の後任だという。近年では、創立50周年の記念式典をはじめ、第74回保健文化賞の受賞(第一生命主催)、長野県知事から社会福祉功労団体として表彰されている。「声を取り戻す」。声帯があれば何でもない、大きな試練に立ち向かうみなさんに、いままでの感謝と今後の活躍を心から祈念したい。いつ誰かが、この団体に入会するか分からないことを、世間にも周知してもらうとよいと思う。『長野県信鈴会』・・・団体名称である。
高齢者で入院経験がある人なら、存じているかもしれない。言葉や聞こえの問題、食べる、飲み込むといった動作に障害のある人に対して、専門的な支援や援助を行う専門職(リハビリテーション)が『言語聴覚士(略してST)』だ。自分も例外ではなく、養護学校在学中から関わりを持つ。このころ資格は存在せず知識を習得した教員が、主に口の動かし方やガムを用いて嚙むといった練習に徹した。昨年の秋ごろから、顔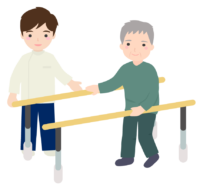 見知りのST(言語聴覚士)さんが2カ月に一度、わが家へ訪問するようになる。「咽喉蓋(いんこうがい)がペラペラ(薄くて弱い)の状態です。食事のとき、唾液を飲み込んだりすると蒸せることがあるでしょうね」。喉の内部を手書きで描きながら、さらに話し続ける。「食道と気管の通り道が若干、狭くなっています。そのために、食べ物などが気管側へ入ったとしても、食道へ入り直すようなしくみになっています」。先天性の変異構造があって、高齢者や脳性まひの嚥下障害を否定した。「あなたと同じ状態の人がほかにもいます」。最後に安堵の一言が耳に入る。その通りかなと・・・。急性咽喉蓋炎とは異なる。一方で、頚髄症の固定術を受けた前後に思いが戻る。顎を上下に動かす、顔を横に向くことができたころは、いまよりは蒸せる確率は少なかったのではないか。首の角度を変えながら、よりベストな食事方法を、自分で決めていたと思う。それが可能でなくなり、食べる姿勢が一転した。飲み込む方はまだましで、動かせない首を気にしながら、3度の食事を頬張ることは並大抵ではない。一通りにまとめると、身体ができる段階で背負ったもの(未熟児形成)、頚髄症に至るまでの二次障害(脳性まひ後遺症)、首の固定術をしたあとの不都合(終身後遺症)が重なり合って、いまの自分があるのだと感じている。風邪気味から咳が出る以外、蒸せるのは承知済みで、よく嚙みながら食事をおいしく食べる。「食べることを練習してください」。手術を受けた信州大学医学部付属病院の医師からもらった、一言をずっと胸に刻みたい。 見知りのST(言語聴覚士)さんが2カ月に一度、わが家へ訪問するようになる。「咽喉蓋(いんこうがい)がペラペラ(薄くて弱い)の状態です。食事のとき、唾液を飲み込んだりすると蒸せることがあるでしょうね」。喉の内部を手書きで描きながら、さらに話し続ける。「食道と気管の通り道が若干、狭くなっています。そのために、食べ物などが気管側へ入ったとしても、食道へ入り直すようなしくみになっています」。先天性の変異構造があって、高齢者や脳性まひの嚥下障害を否定した。「あなたと同じ状態の人がほかにもいます」。最後に安堵の一言が耳に入る。その通りかなと・・・。急性咽喉蓋炎とは異なる。一方で、頚髄症の固定術を受けた前後に思いが戻る。顎を上下に動かす、顔を横に向くことができたころは、いまよりは蒸せる確率は少なかったのではないか。首の角度を変えながら、よりベストな食事方法を、自分で決めていたと思う。それが可能でなくなり、食べる姿勢が一転した。飲み込む方はまだましで、動かせない首を気にしながら、3度の食事を頬張ることは並大抵ではない。一通りにまとめると、身体ができる段階で背負ったもの(未熟児形成)、頚髄症に至るまでの二次障害(脳性まひ後遺症)、首の固定術をしたあとの不都合(終身後遺症)が重なり合って、いまの自分があるのだと感じている。風邪気味から咳が出る以外、蒸せるのは承知済みで、よく嚙みながら食事をおいしく食べる。「食べることを練習してください」。手術を受けた信州大学医学部付属病院の医師からもらった、一言をずっと胸に刻みたい。
全盲の人の暮らしと、喉に関係するハンディについて書いてみた。どれもこれも試練の連続で、たゆまぬ努力の結晶であると同時に、それを普通の事柄と前向きにとらえ、歩む姿が光って見えてきそうだ。障害という言葉を用いる前に、誰もが一人の人間であることを確認できたらよい。「何か食べたいものはありますか?」。食材や日用品の買い物をしてもらう際、ヘルパーさんから聞く言葉である。今回の会話はこうだ。 「(私)松茸ご飯がいいなぁ」→「そんなもん高価過ぎてダメだよ」→「じゃあ、松茸めしの素をお願いします」。さあ、電気炊飯器にセットするときだ。ご飯の水加減を少なめでお願いしたところ、思っていた以上にボロボロなご飯となってしまった。いつもの心の一言「物事はこんなものか!」と思いながら、今秋の松茸ご飯を舌鼓することができた。 「(私)松茸ご飯がいいなぁ」→「そんなもん高価過ぎてダメだよ」→「じゃあ、松茸めしの素をお願いします」。さあ、電気炊飯器にセットするときだ。ご飯の水加減を少なめでお願いしたところ、思っていた以上にボロボロなご飯となってしまった。いつもの心の一言「物事はこんなものか!」と思いながら、今秋の松茸ご飯を舌鼓することができた。
2024/10/30
|