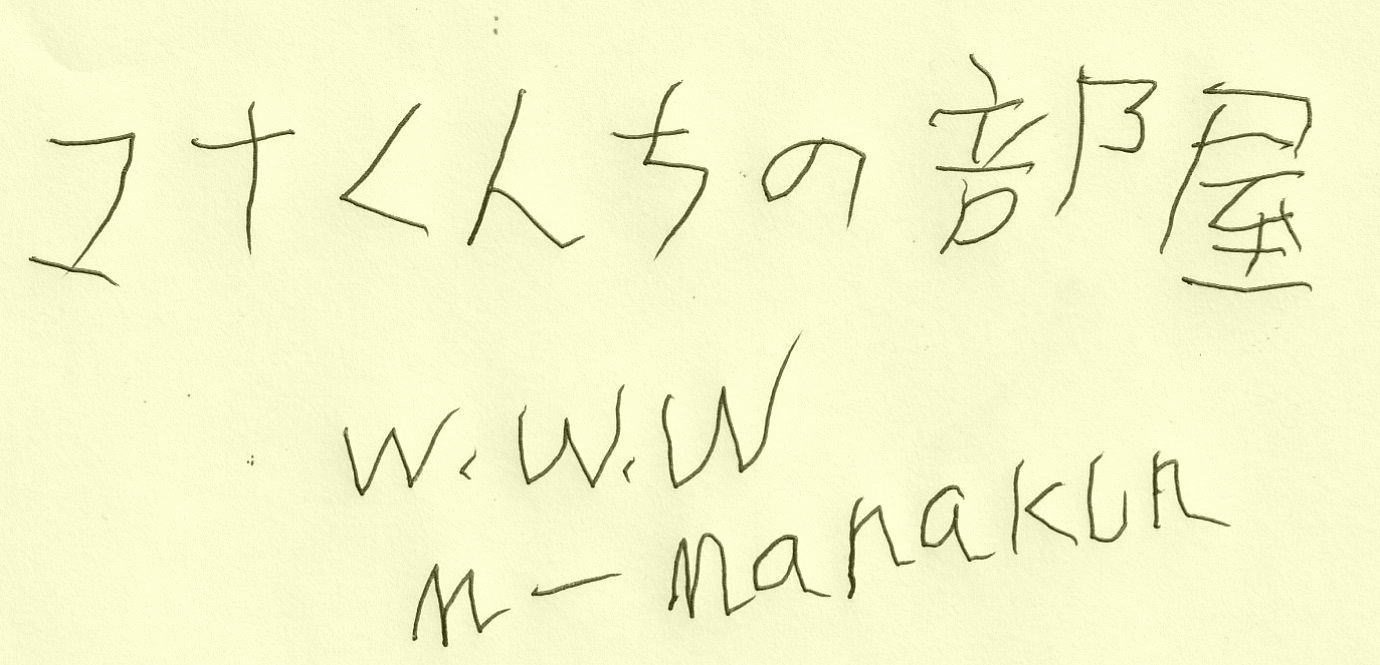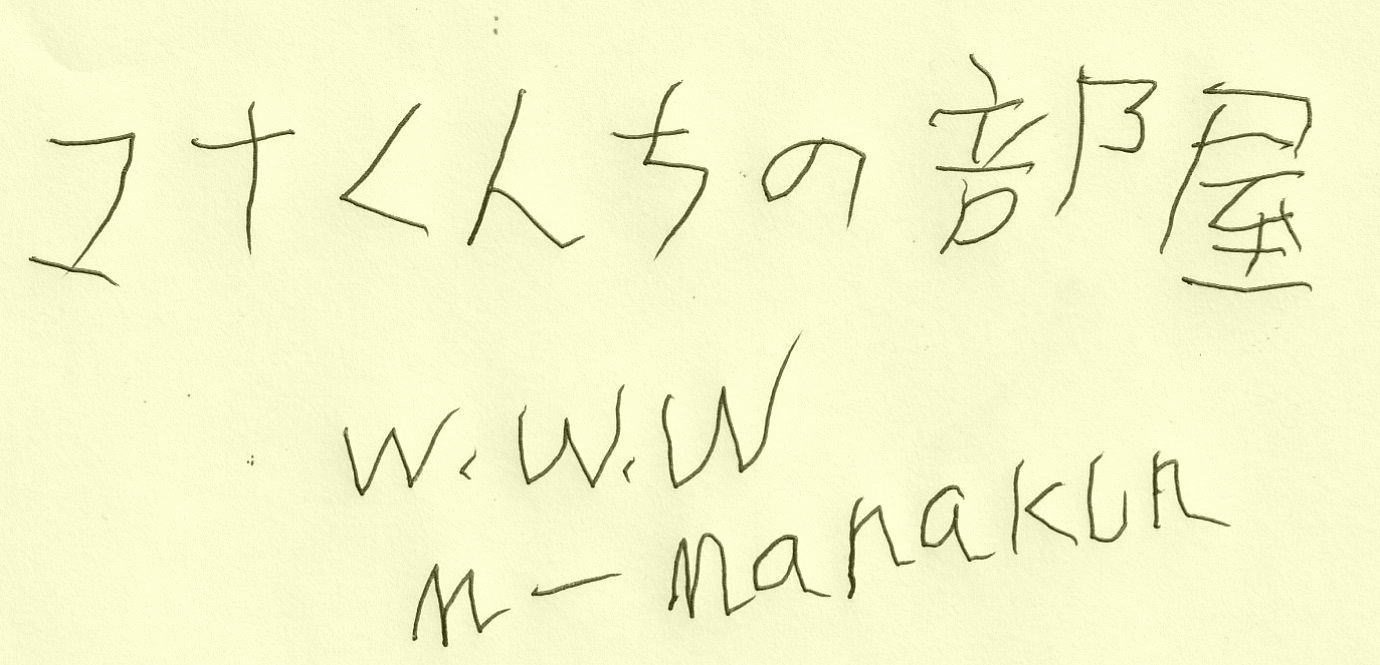|
「ああっ、歩いている・・・」。思わず口から出た。片手に果物を持って一瞬、背を真っすぐして二歩、三歩と前進していく。飯田市立動物園のサル山で、ライブカメラがとらえた動画。普段、テレビかネット動画でしかお目にかかれない『猿まわし』の一部分の芸が、地元の動物園で楽しめた。私たち人間の先祖は猿とも言われるし、身体の仕組みではチンパンジーがより近いらしい。血液型で分かる参考書では『周りに気を配る』性格にヒットする。こういう私は、その逆が出てしまうことも・・・。小学低学年のころ、両親に連れられて耳鼻科医院へ行く。待合室で松葉杖の患者さんを見るなり、人差し指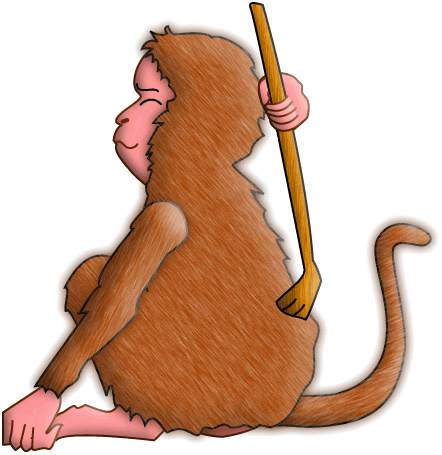 を向けながら軽々しく暴言を吐く。「そういうお前は何でもできるのか」。父からの注意に返事ができず、泣き出しそうになる。慰めるしぐさもない母もまた冷静。自分の眼(まなこ)は、世の中のことを知らない幼稚なものであった。いまも思い出すシーンと私の一言は、脳裏に刻み込まれた。(松葉杖の患者さんに)「あれっなんだ。あんな格好で歩くのか」。 を向けながら軽々しく暴言を吐く。「そういうお前は何でもできるのか」。父からの注意に返事ができず、泣き出しそうになる。慰めるしぐさもない母もまた冷静。自分の眼(まなこ)は、世の中のことを知らない幼稚なものであった。いまも思い出すシーンと私の一言は、脳裏に刻み込まれた。(松葉杖の患者さんに)「あれっなんだ。あんな格好で歩くのか」。
令和6年初秋、いつもの感覚でショートスティの玄関へ入ったら、見かけない男性利用者さんと鉢合わせになる。その人は眼鏡をしていて、履いているズボンには立派なベルトを巻いていた。なりゆき任せで所長さんに聞いてみると、会社の社長さんだとか・・・。それは恐れ入ったと思いきゃ話は続く。「(奥様が)困っていて、ここ(ショ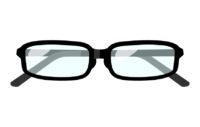 ート)で引き受けたの」。徘徊行動があるみたいで、サッシのロックが解除されているところから無断で外へ出ていく。少し見ただけでは気づかなかった。以前では痴ほう症とも言われていたが、差別的だとして病名が改められる。認知症とはいったい何のか、分かる範囲で書き出してみたい。 ート)で引き受けたの」。徘徊行動があるみたいで、サッシのロックが解除されているところから無断で外へ出ていく。少し見ただけでは気づかなかった。以前では痴ほう症とも言われていたが、差別的だとして病名が改められる。認知症とはいったい何のか、分かる範囲で書き出してみたい。
脳に障害が生じることで起きる症状で、原因によっていくつかの病気が認知症となる。トップの67.6パーセントが『アルツハイマー病』だ。徐々に神経細胞が減って脳の働きが低下していく。病魔の正体は、アミロイドβというタンパク質で溜まり続けると重症化する。糖尿病や高血圧症、甘いものを好むなど、大きく関与しているが生活習慣だ。はじめは顕著なもの忘れ、カレンダーの情報や自分の居場所が分からなくなり、腕前だった料理も作れない。うつ、不安、怒りっぽい、暴言、暴力、ひとり歩き(徘徊)が症状で、ゆっくり進行していく。脳出血、脳梗塞のため、脳の神経細胞が障害を受けて起きるのが『血管性認知症』。主に身体が不自由になるのが特徴で、ダメージの部位によって認知障害も現れる。新たな出血や梗塞のたびに症状が悪化。『レビー小体型認知症』は、アルツハイマー病の原因と類似していて、タンパク質αシヌクレインが脳細胞に溜まり続け、認知機能に低下を来す。実際には存在しないものが見える(幻視)、手の震え、動作がゆっくり、筋肉がこわ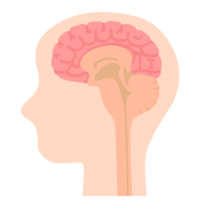 ばる、睡眠中に大声で寝言を言う、手足を激しく動かす、よいときと悪いときの差が激しい、薬剤に対する過敏性が強いなどを症状とする。前者と似通った原因がある、もう一つの認知症は『前頭側頭型認知症(ピック病)』。タウやTDP-43と呼ばれるタンパク質が異常に溜まり、脳の前方(前頭葉と側頭葉)が萎縮し働きを弱めることで発病。みられる症状としては、性格が自己中心的、他人への思いやりがなくなり社会のルールを守れない、日々の行動のパターン化、食べ過ぎるなど・・・。ほかに、65歳未満で発症する『若年性認知症』患者が全国に3.57万人いると言われ、この先もすべての認知症が増える予想で、もはや、国民病の一つともなりうる。 ばる、睡眠中に大声で寝言を言う、手足を激しく動かす、よいときと悪いときの差が激しい、薬剤に対する過敏性が強いなどを症状とする。前者と似通った原因がある、もう一つの認知症は『前頭側頭型認知症(ピック病)』。タウやTDP-43と呼ばれるタンパク質が異常に溜まり、脳の前方(前頭葉と側頭葉)が萎縮し働きを弱めることで発病。みられる症状としては、性格が自己中心的、他人への思いやりがなくなり社会のルールを守れない、日々の行動のパターン化、食べ過ぎるなど・・・。ほかに、65歳未満で発症する『若年性認知症』患者が全国に3.57万人いると言われ、この先もすべての認知症が増える予想で、もはや、国民病の一つともなりうる。
では、治療はどうなっているか。現在、先端となる薬物療法は疾患修飾薬といい、原因そのものを取り除き病気の進行を抑える効果を持つ。早期のアルツハイマー病に対し新薬として、2023年12月に発売となった。中期・重症化のアルツハイマー病やその他 の認知症では、残存する神経細胞を刺激し認知機能を改善する症状改善薬が薬物療法となっている。並行して行われるのが非薬物療法で、適切な生活環境を保つためのケアを受けることがそれにあたり、介護保険サビースでデイサービスの利用も検討していく。その人らしさを尊重するパーソンセンタードケアである。(以上、医学的情報はネットサイト「認知症ABC」からの部分抜粋) の認知症では、残存する神経細胞を刺激し認知機能を改善する症状改善薬が薬物療法となっている。並行して行われるのが非薬物療法で、適切な生活環境を保つためのケアを受けることがそれにあたり、介護保険サビースでデイサービスの利用も検討していく。その人らしさを尊重するパーソンセンタードケアである。(以上、医学的情報はネットサイト「認知症ABC」からの部分抜粋)
罹患してからではなく予防を心がけたい。実際に100歳になっても、認知症の症状がみられない人もいる。原因とされる生活習慣へ導かないことが大切。全体の半分以上を占めるアルツハイマー病のリスクを理解し、穏やかに楽しい時間を過ごす。調査と研究によれば、睡眠不足からアミロイドβが脳内に寄せ集まっていくとも言われ、家屋に存在するカビとの関係も否定できないとされる。またそれに敏感にならず、何か趣味を持ち頭の体操に専念したいものだ。
会社の社長さんは2泊3日のショート利用を終えて、奥さんのもとへ帰っていく。入れ替わるかのように、同じく眼鏡をかけた別の男性利用者が奥様と同伴で訪れ、私と初対面。承知のうえで時折、視線を向けた。サッシはロックをしてあるけれど、落ち着きなく椅子から立つと、それ(ロック)に気づかず、いつまでも懸命に開けようと必死の模様。座ったテーブルの前に、出来立ての食 事が置いてあるのに手をつけず、また立ち上がりふらふら歩く。時には足が車いすや押し車に引っ掛かり転びそうになってしまう。その利用者さんを元の席に連れて行き、所長さんも横で食事をはじめる。安心したみたいで、2人ともおいしそうに頬張っていた。こんな繰り返しで、夕食後は服用薬の効果があり、ぐっすりおやすみのようだ。つぎの日の午前中、毎度一緒になる少し大柄の女性利用者さんが訪れる。何だか自分までが落ち着かない。1日前から滞在中の眼鏡をかけたおじさんと、到着したばかりのおばさんに気を奪われてしまう。この2人に注目をするのか。最初は距離を置く両者だが、少し経つとおばさんが前かがみになっているおじさんの背中や腰を手で思いっきり叩く。痛がりやびっくりともせずに、表情を変えないおじさん。夜になって2人が、フロアの椅子に座り向き合っているところを目撃。笑みを浮かべるおじさんに、おばさんは両手を叩きうれしそう。触れ合いという素敵な場面に出会う。同時に感動を覚え、自分も彼らとよい関係を持ちたいという気持ちが芽生えはじめた。 事が置いてあるのに手をつけず、また立ち上がりふらふら歩く。時には足が車いすや押し車に引っ掛かり転びそうになってしまう。その利用者さんを元の席に連れて行き、所長さんも横で食事をはじめる。安心したみたいで、2人ともおいしそうに頬張っていた。こんな繰り返しで、夕食後は服用薬の効果があり、ぐっすりおやすみのようだ。つぎの日の午前中、毎度一緒になる少し大柄の女性利用者さんが訪れる。何だか自分までが落ち着かない。1日前から滞在中の眼鏡をかけたおじさんと、到着したばかりのおばさんに気を奪われてしまう。この2人に注目をするのか。最初は距離を置く両者だが、少し経つとおばさんが前かがみになっているおじさんの背中や腰を手で思いっきり叩く。痛がりやびっくりともせずに、表情を変えないおじさん。夜になって2人が、フロアの椅子に座り向き合っているところを目撃。笑みを浮かべるおじさんに、おばさんは両手を叩きうれしそう。触れ合いという素敵な場面に出会う。同時に感動を覚え、自分も彼らとよい関係を持ちたいという気持ちが芽生えはじめた。
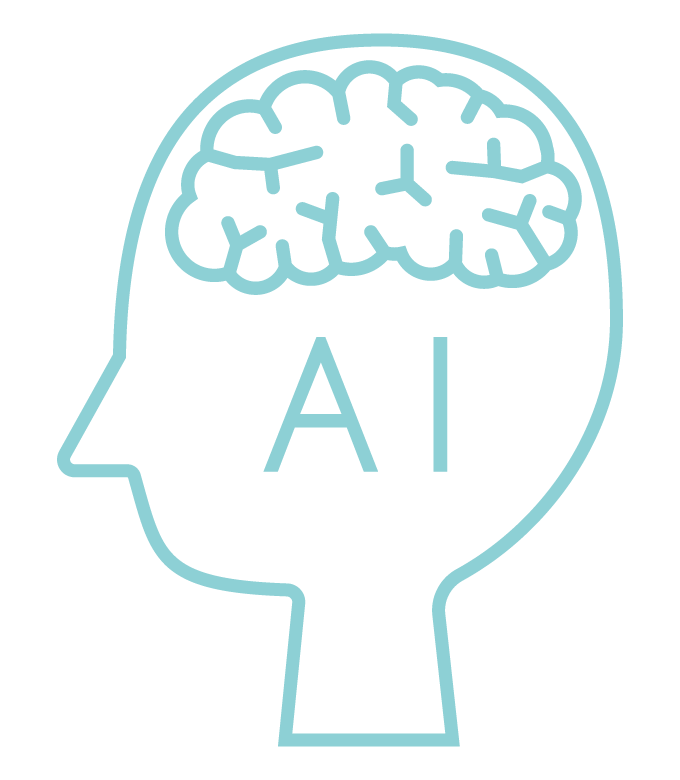 何からやればよいのか。触れ合うための基本は、理解できる範囲での病気知識と接し方の方法で、それらを覚えていくことが大切だと思う。介護職員向けの接し方情報をネットAIが回答してくれた。「①短くて分かりやすい言葉を使い、同じことを何度も繰り返しても恐れず、根気よく対応。②落ち着いた声で話しかけると相手に安心感を与え、
笑顔で接していけば相手もリラックスしやすい。③言葉だけでなく、ジェスチャーや視覚的な手がかりを使ってコミュニケーションを補助し、手を握るなどの優しい触れ合いは安心感を与える。④一人の人間として尊重し、プライドを傷つけないように向き合う。⑤相手の気持ちに寄り添い共感を示せれば信頼関係を築くことが可能」。しかし、実践となると簡単ではなく個々での対応が必要か。情報に気を取られ過ぎでもいけないだろうし、身近にいるベテランからのアドバイスを受け、自然に接することで触れ合いの道が開けるケースも・・・。「社会を支えてきた先輩と接する喜びを体験する」。そんな思考から、よいつながりを探求していきたい。 何からやればよいのか。触れ合うための基本は、理解できる範囲での病気知識と接し方の方法で、それらを覚えていくことが大切だと思う。介護職員向けの接し方情報をネットAIが回答してくれた。「①短くて分かりやすい言葉を使い、同じことを何度も繰り返しても恐れず、根気よく対応。②落ち着いた声で話しかけると相手に安心感を与え、
笑顔で接していけば相手もリラックスしやすい。③言葉だけでなく、ジェスチャーや視覚的な手がかりを使ってコミュニケーションを補助し、手を握るなどの優しい触れ合いは安心感を与える。④一人の人間として尊重し、プライドを傷つけないように向き合う。⑤相手の気持ちに寄り添い共感を示せれば信頼関係を築くことが可能」。しかし、実践となると簡単ではなく個々での対応が必要か。情報に気を取られ過ぎでもいけないだろうし、身近にいるベテランからのアドバイスを受け、自然に接することで触れ合いの道が開けるケースも・・・。「社会を支えてきた先輩と接する喜びを体験する」。そんな思考から、よいつながりを探求していきたい。
そっちのけも甚々しい。第一、自分の認知機能を知らなくてどうする。「自分でできる!かんたん認知症チェック」サイトから、テストを受けてみた。機能低下はなしとの結果だったが、自己検査だけでなく支援者・ヘルパーさんの評価が出ないと、はっきりしそうにもない。かんたんチェックに気づいたのは、9月20日夜、NHK総合で放送された『首都圏情報ネタドリ!…新常識・認知症は早期に予防せよ』で、自身の体験を語る俳優・山本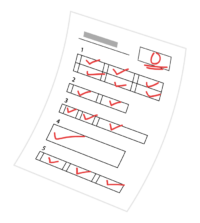 學さんが運動や食事改善の大切さに触れ「身体を動かすためにできる体操を行い、バランスのよい食事を心がけていくと、幻視が消え物忘れもなくなった」と語っていた。同席の医師はより詳しい最新情報を紹介する。新薬についてのほか、VRゴーグルを使った検査があるらしい。症状が軽いうちほど完治に近い値までいくと言い、自分の認知機能を確かめておくことと生活習慣に気を配れば、高齢となっても予防につながると話す。罹患する危険は誰にもあり、身近な老化現象であるととらえたい。 學さんが運動や食事改善の大切さに触れ「身体を動かすためにできる体操を行い、バランスのよい食事を心がけていくと、幻視が消え物忘れもなくなった」と語っていた。同席の医師はより詳しい最新情報を紹介する。新薬についてのほか、VRゴーグルを使った検査があるらしい。症状が軽いうちほど完治に近い値までいくと言い、自分の認知機能を確かめておくことと生活習慣に気を配れば、高齢となっても予防につながると話す。罹患する危険は誰にもあり、身近な老化現象であるととらえたい。
こうすると、こうなるのか(こう話すと、こう返ってくるかな)・・・。周りを見ながら気を配る(遣う)ハートの小さな人間が、一転して傲慢な気持ちになる。「あれっ、(おじさんとおばさんが)来たぞ」。警戒感と好奇心が入り乱れていく。心の内を何とかできないものか。たったの一つの心構えは、ショートスティへくる10人余りの利用者さんは、一軒家で暮らす構成員の人たちであると・・・。
2024/09/29
|