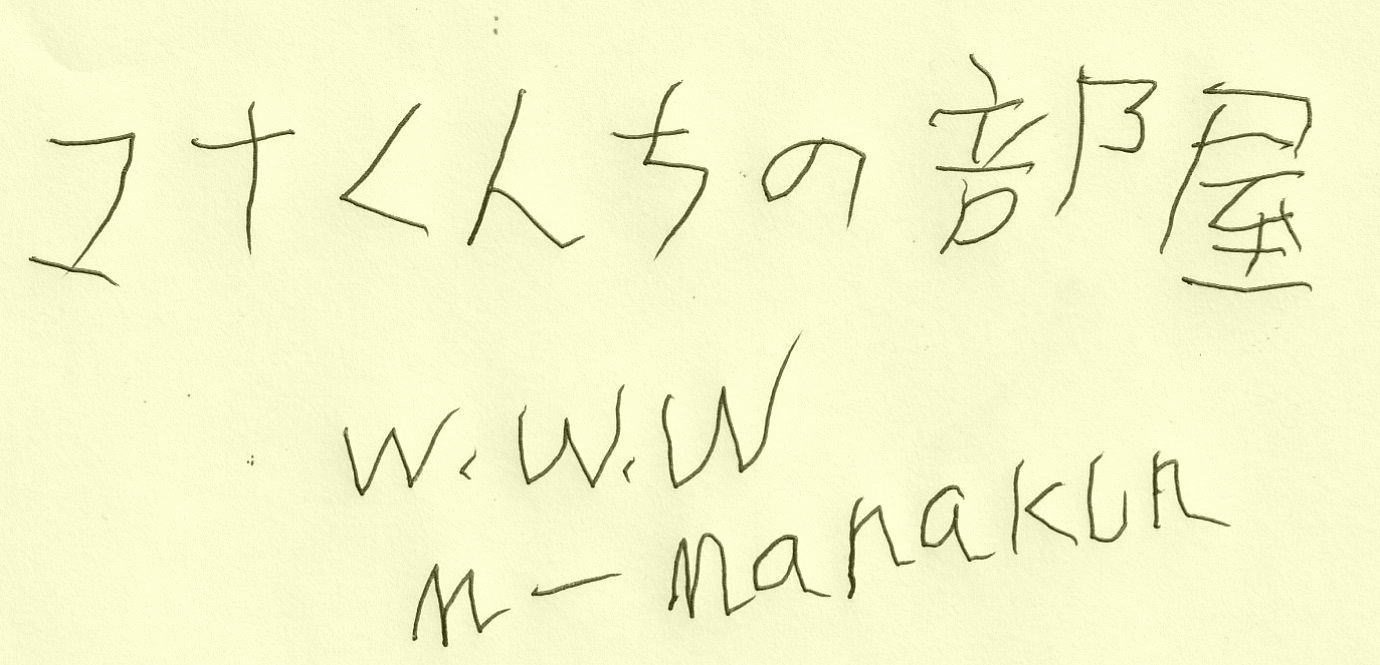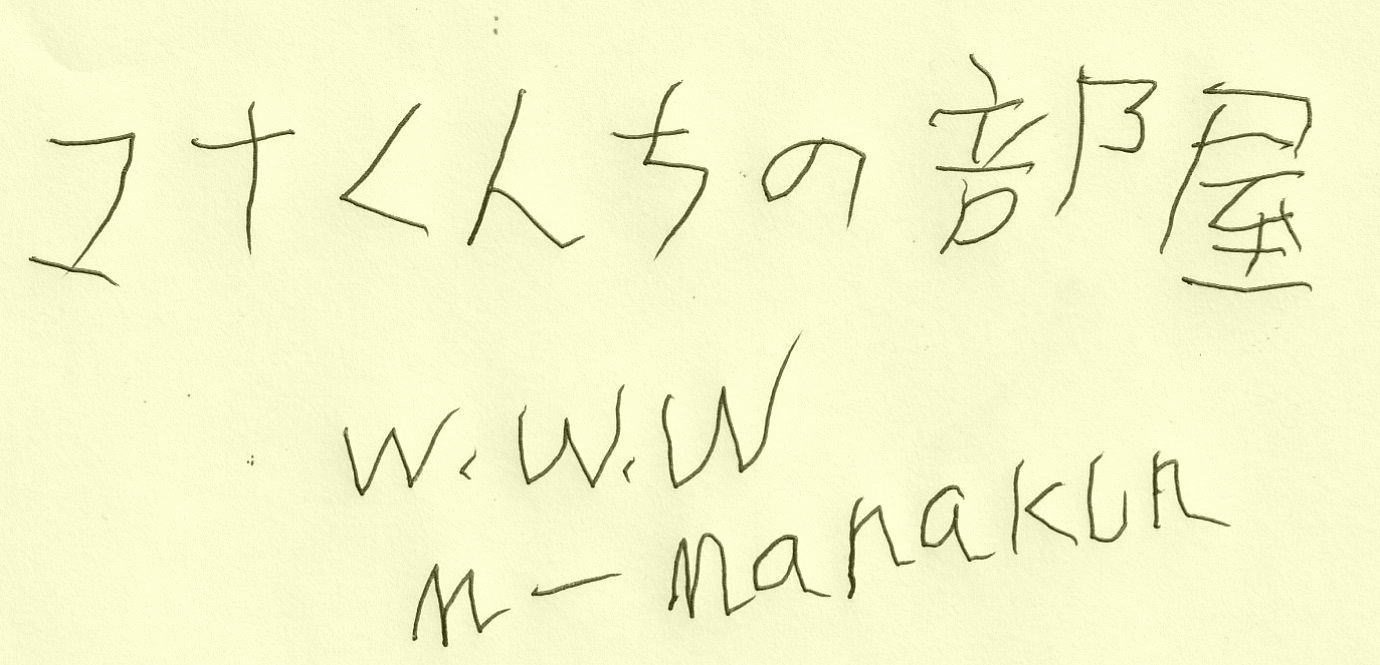|
ピンク色のカーテンで仕切りをした4人部屋。自分がいるところは、窓側ではないので日中でも薄暗い。この場所だと気が沈みがち。おまけに身体は熱っぽいし、とにかくだるい。電動車いすに身を預けるようにしながら、個人ロッカーに設置されたカードタ イマー付きのテレビへ目を向けている。すると、画面内容が変わった。「宮崎県日向灘でやや強い揺れ。つなみ、にげて!(津波警報発令中)」。地震速報が飛び込んできた。「九州のことか」。楽観な思いでいたら、事前避難対象地域となっている。ただただ、唖然。 イマー付きのテレビへ目を向けている。すると、画面内容が変わった。「宮崎県日向灘でやや強い揺れ。つなみ、にげて!(津波警報発令中)」。地震速報が飛び込んできた。「九州のことか」。楽観な思いでいたら、事前避難対象地域となっている。ただただ、唖然。
令和6年8月8日夕暮れ、南海トラフ巨大地震臨時情報がはじめて、気象庁から発表された。翌日夜のニュース時間帯には、神奈川県でも揺れが生じる。総理官邸からの中継となって、岸田首相が注意を呼びかける。相模トラフ巨大地震が併せて起きるのか。こうなると、自然に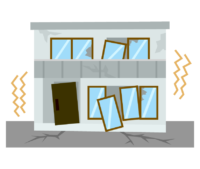 小松左京著のSF(空想科学)小説『日本沈没』を思い浮かべてしまう。映画を見たのは確か中学生のころで、私は家族に話す。「最後に沈むのはここら辺らしいので、落ち着いていいと思うよ」。避難はどうするかと問わられて、船か飛行機に乗って逃げるしかないと素直顔で答えた。 小松左京著のSF(空想科学)小説『日本沈没』を思い浮かべてしまう。映画を見たのは確か中学生のころで、私は家族に話す。「最後に沈むのはここら辺らしいので、落ち着いていいと思うよ」。避難はどうするかと問わられて、船か飛行機に乗って逃げるしかないと素直顔で答えた。
防災の日。いまから100年前に起きた関東大震災は、9月1日だったことが由来となっている。制定日の内容を引用してみた。「日本が過去に経験した大規模な災害の認識を深め、これに対処する心構えを準備し、災害に備えるために制定された日です。マグニチュード7.9と推定され、東京や横浜を中心に甚大な被害をもたらしました。死者・行方不明者は約10万5000人にのぼり、特に火災による被害が大きかったです(ネットから抜粋)」。喬木村でも、総合防災訓練 が毎年あり、同時に地区の組合ごとに実施される安否確認、情報伝達訓練にも参加を呼びかけている。まだ暑さが残るこの日に、集合場所まで自力で歩くのは一苦労だった。ノロノロ台風10号の影響から、村内の訓練がすべて中止となった今年。さまざまな事柄が重なり合い、それが偶然だとはしても、巨大地震の前触れかと思わせる情報が飛び交い、悪夢の中の現実を直観する。まったくSFそのものかも・・・。 が毎年あり、同時に地区の組合ごとに実施される安否確認、情報伝達訓練にも参加を呼びかけている。まだ暑さが残るこの日に、集合場所まで自力で歩くのは一苦労だった。ノロノロ台風10号の影響から、村内の訓練がすべて中止となった今年。さまざまな事柄が重なり合い、それが偶然だとはしても、巨大地震の前触れかと思わせる情報が飛び交い、悪夢の中の現実を直観する。まったくSFそのものかも・・・。
8月はじめ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と診断される。この流行疾患が日本で広まるようになり4年目、自身には最初の感染であった。予防接種をその都度受けてはいたが、感染症法上の「5類感染症」に位置づけられてからワクチン注射はしていなかった。まさかのできごとを、そのまま受け止めている。短期入所施設へ行って2日目、お風呂から上がると急に咳の回数が増え、夜はなかなか寝つかれなかった。午前2時半、介護職員を呼び、電動車いすへ乗る手伝いをしてもらう。姿勢を少し前かがみにすると、楽になり咳が止まる。加え て、咳止めと熱さましの薬を求める。「まだまだ(服用の)時間が来ないから、朝食まで待ってください」。分かってはいたが、不調には勝てず、我慢するしかほかになかった。つぎの日、お昼の時報が鳴ったころ、所長さんが私のいる部屋へ入ってくる。「○○(所長さんの名字)です。これから病院へ行って診てもらいましょう」。所長さんの運転するワゴン車で、かかりつけの病院へ着く。院内の発熱外来診察室で所長さんと一緒にいると、女性医師が私に尋ねた。その問いかけに、だるいし咳が出ると症状について話す。「何日か安静が必要ですね」。「やはり入院だろう」と、自分を慰める。ずっと横にいてくれた所長さんが見せた、手を振りながらのバイバイのジェスチャーは、無言の励ましであったと思う。のちに知った所長さんへの感染、施設の利用者さん、スタッフの方々に大変な迷惑をしてしまった。自分が把握していない感染についても、この場で深くお詫びを申し上げたい。 て、咳止めと熱さましの薬を求める。「まだまだ(服用の)時間が来ないから、朝食まで待ってください」。分かってはいたが、不調には勝てず、我慢するしかほかになかった。つぎの日、お昼の時報が鳴ったころ、所長さんが私のいる部屋へ入ってくる。「○○(所長さんの名字)です。これから病院へ行って診てもらいましょう」。所長さんの運転するワゴン車で、かかりつけの病院へ着く。院内の発熱外来診察室で所長さんと一緒にいると、女性医師が私に尋ねた。その問いかけに、だるいし咳が出ると症状について話す。「何日か安静が必要ですね」。「やはり入院だろう」と、自分を慰める。ずっと横にいてくれた所長さんが見せた、手を振りながらのバイバイのジェスチャーは、無言の励ましであったと思う。のちに知った所長さんへの感染、施設の利用者さん、スタッフの方々に大変な迷惑をしてしまった。自分が把握していない感染についても、この場で深くお詫びを申し上げたい。
わが身はエレベーターで3階病棟に入った。入院は2年前以来である。何だか懐かしいやら、これでよいのか、時に任せるしかないと判断。本年1月にもらった、支援者Cさんの一言を思い出す。「入院ともなれば、覚悟をしてください。(期間は)最低でも1カ月はかかりますよ」。今度のありさまと比較することができるか、迷いが交差する。看護師さんに聞いてみた。返事は2週間ほどだとか・・・。「ひょっとしたら、ショート期間中に施設へ戻れるかな」。淡い期待が膨らむ。新型コロナウイルス治療薬を服用してから、瞼を閉じると、自分が怖いと思うシーンが連続して現れたので(幻覚?)、夜は眠れず睡眠薬に頼る。当初は熱があり、何もする気がなく、食事はベッド上で介助食を頬張る。のちに、自力で食事を摂るようになってからも、軟飯、刻みの副食が食膳に並ぶ。 「こんなご飯を食べていたのか」。病院とのつながりがあった時期が鮮明によみがえった。「普通食に変更していただきたい」。伝えたい言葉が口元まで出そうなのに、何故かしまっておく。が、いまとなっては後悔のみ。頭に描いていた通り、再びショート施設へ戻る日がきた。10日間の入院暮らしを経て、4人部屋を仕切るピンクのカーテンに別れを告げる。エレベーターの前まで行くと、お迎えにきたCさんの笑顔があった。 「こんなご飯を食べていたのか」。病院とのつながりがあった時期が鮮明によみがえった。「普通食に変更していただきたい」。伝えたい言葉が口元まで出そうなのに、何故かしまっておく。が、いまとなっては後悔のみ。頭に描いていた通り、再びショート施設へ戻る日がきた。10日間の入院暮らしを経て、4人部屋を仕切るピンクのカーテンに別れを告げる。エレベーターの前まで行くと、お迎えにきたCさんの笑顔があった。
短期入所施設で残り2日間を過ごし、わが家へ帰る。倦怠あるいは疲労感があって、何かしようとしてもや る気が起きない。そんな中、高森町在住で母方のいとこが訪ねてくる。何やらと思いきゃ、悲しい知らせを持ってきた。「飯田市に住むいとこのお嫁さんが亡くなったの。お別れの会を、親しい友人だけに集まってもらい執り行いました」。本年の年賀状は住所不詳で戻ってきていた。お嫁さんは沖縄・石垣島出身で、いとことは愛知県瀬戸市で出会う。瀬戸焼(せとやき)で有名なところで、ご主人でもある彼は先輩から陶磁器の指導を受けていた。また交流を好み、サークル活動に精力的な参加をして、そこで2人は同じ気持ちを確認し合う。お嫁さんは当時、私と同じ二十歳(はたち)だった。一部分に過ぎないけど、ちょっぴりいとこ夫婦と似たテレビドラマストリーの再放送をいま観ている。主人公の恵里は正看護師として活躍し、同じ病院に勤務する文也と永遠の愛を誓う。団結力を感じさせる沖縄独特の家族愛に触れながら、恵里と文也が築いていく新しいファミリー考を描く物語。はじまりは、共に小学生高学年の時期で、文也の兄が短い命と告知を受け、恵里の親が経営する民宿へ家族旅行の名目で何日か滞在し、知らない同士が仲よしになっていく。恵里の祖母・おばぁは、不思議な想像力を持ち、ヒロインからかかってくる電話の予測をするなどして、本人(恵里)に語りかけるナレーションがまた光っている。父や兄、弟役も個性的で、流れの中で笑いと笑顔を誘う。沖縄から上京してアパート暮らしをスタートさせ、同居者との触れ合い、支えあいが恵里を成長させていく。(再放送の第102回あたりまでの内容を記する)本放送を見た覚えはあるが今回、おもろしさに夢中となってしまった。いとこのお嫁さんも準看護師として働き、女の子と男の子を授かる。ある日、いとこ夫婦から夕食会に招かれた。「一つだけ、聞いてほしい。こつい る気が起きない。そんな中、高森町在住で母方のいとこが訪ねてくる。何やらと思いきゃ、悲しい知らせを持ってきた。「飯田市に住むいとこのお嫁さんが亡くなったの。お別れの会を、親しい友人だけに集まってもらい執り行いました」。本年の年賀状は住所不詳で戻ってきていた。お嫁さんは沖縄・石垣島出身で、いとことは愛知県瀬戸市で出会う。瀬戸焼(せとやき)で有名なところで、ご主人でもある彼は先輩から陶磁器の指導を受けていた。また交流を好み、サークル活動に精力的な参加をして、そこで2人は同じ気持ちを確認し合う。お嫁さんは当時、私と同じ二十歳(はたち)だった。一部分に過ぎないけど、ちょっぴりいとこ夫婦と似たテレビドラマストリーの再放送をいま観ている。主人公の恵里は正看護師として活躍し、同じ病院に勤務する文也と永遠の愛を誓う。団結力を感じさせる沖縄独特の家族愛に触れながら、恵里と文也が築いていく新しいファミリー考を描く物語。はじまりは、共に小学生高学年の時期で、文也の兄が短い命と告知を受け、恵里の親が経営する民宿へ家族旅行の名目で何日か滞在し、知らない同士が仲よしになっていく。恵里の祖母・おばぁは、不思議な想像力を持ち、ヒロインからかかってくる電話の予測をするなどして、本人(恵里)に語りかけるナレーションがまた光っている。父や兄、弟役も個性的で、流れの中で笑いと笑顔を誘う。沖縄から上京してアパート暮らしをスタートさせ、同居者との触れ合い、支えあいが恵里を成長させていく。(再放送の第102回あたりまでの内容を記する)本放送を見た覚えはあるが今回、おもろしさに夢中となってしまった。いとこのお嫁さんも準看護師として働き、女の子と男の子を授かる。ある日、いとこ夫婦から夕食会に招かれた。「一つだけ、聞いてほしい。こつい と会ったサークルに、脳性まひの障害がある男性がいてね、同じメンバーの健康な女性と結婚したよ。彼女はね、最初ほかに彼氏がいてゴールイン目前にして、いまのご主人を選んだのさ。学君もがんばって・・・」。いとこの温かなエールは、いまもなお新鮮そのまま。恵里ちゃんみたいな彼女を見つけたいなぁ・・・若きころの思い。「美しい、立派なさま(沖縄の言葉)」。NHK連続テレビ小説・第64作「ちゅらさん」と重ね、思い出してみた。 と会ったサークルに、脳性まひの障害がある男性がいてね、同じメンバーの健康な女性と結婚したよ。彼女はね、最初ほかに彼氏がいてゴールイン目前にして、いまのご主人を選んだのさ。学君もがんばって・・・」。いとこの温かなエールは、いまもなお新鮮そのまま。恵里ちゃんみたいな彼女を見つけたいなぁ・・・若きころの思い。「美しい、立派なさま(沖縄の言葉)」。NHK連続テレビ小説・第64作「ちゅらさん」と重ね、思い出してみた。
昨年に続き猛暑となった今夏。3年前の東京大会に継ぐ、パリオリンピックが開幕。テレビ観戦をする母国の私たちに、どの種目でも夢と希望を与えてくれた。8月に入ってからの気に止まったあれこれを書き出す。ペンの走り具合がよく、用紙の余白がたちまち埋まる。暑さが脳を刺激させたのか。毎月、書くことが好きになったとも言えそう。「ひと夏の経験」。百恵ちゃんの歌う詞の意味を考えても、到底自分は関係しない。それでも経験ありの夏であった。
2024/09/27
|