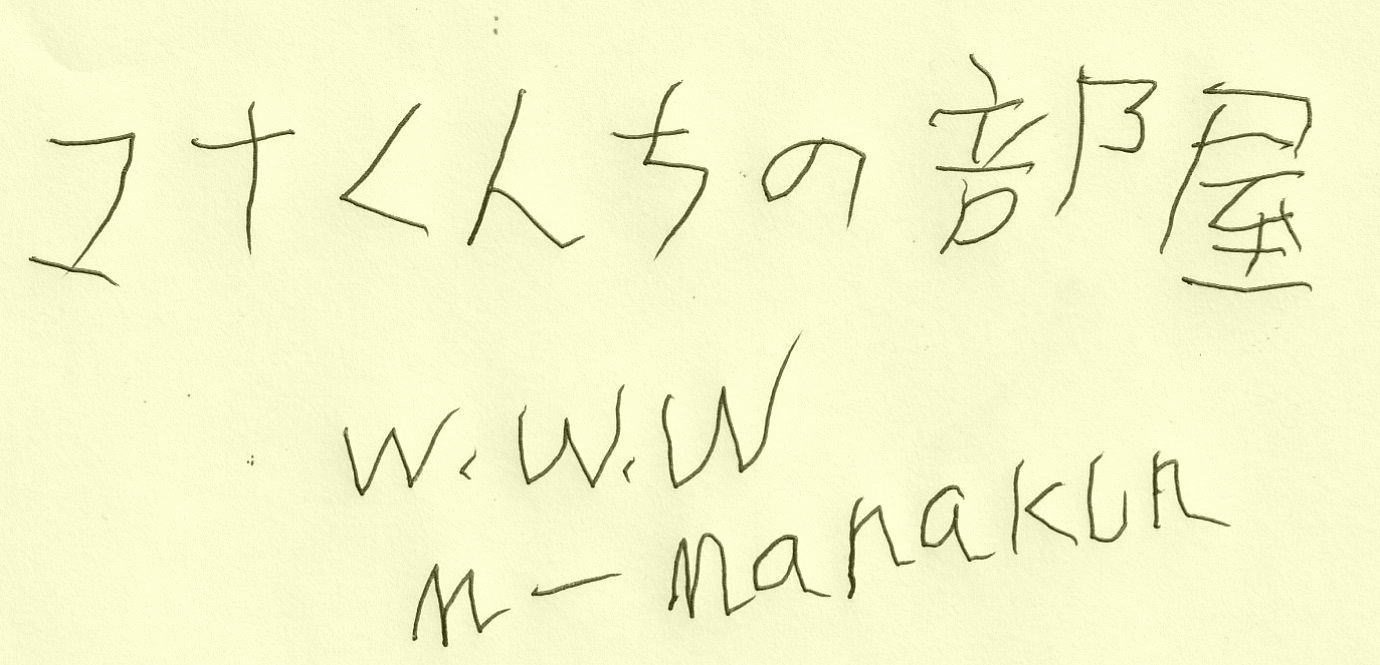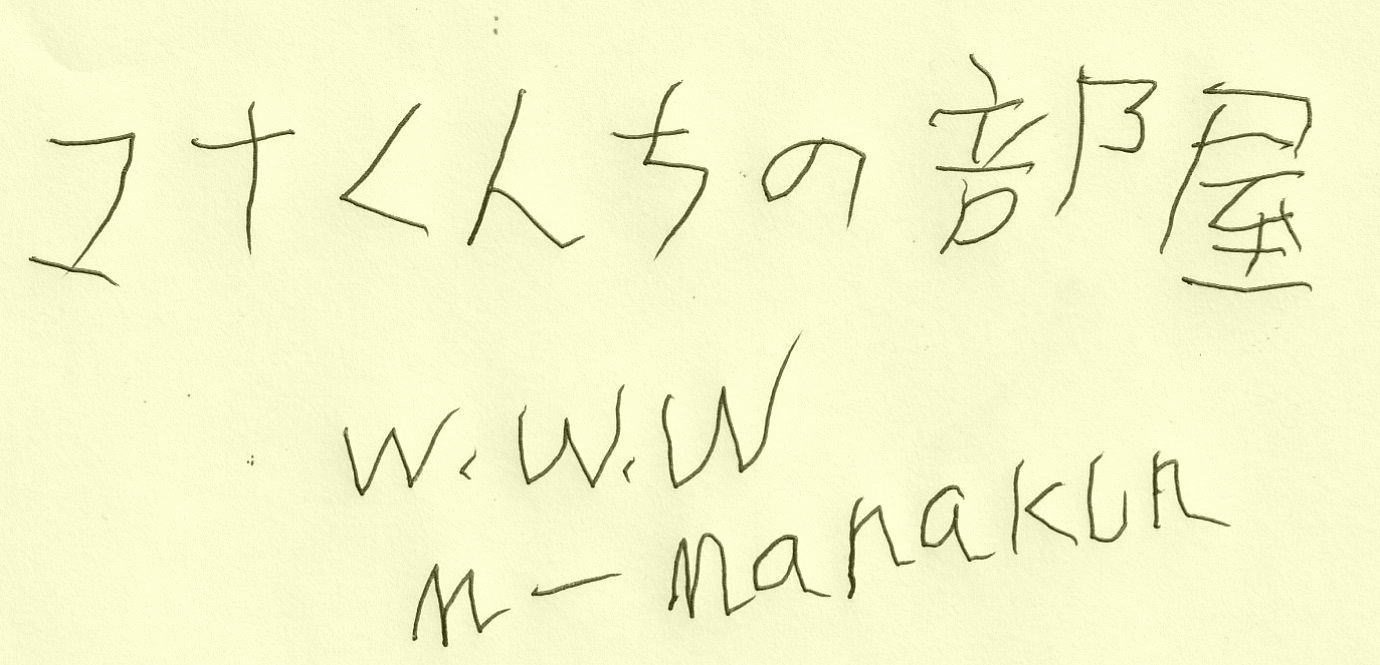|
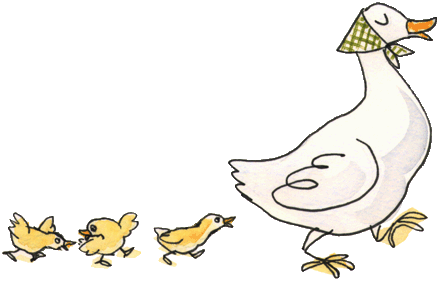 「水タンクの表に背もたれがあり、赤色の便座シートが見える。両側には肘掛けオプションを設置、アヒルが便器の中でゆったりと泳ぎ、コメントには『トイレでスッキリ』と書き記している」。書籍の表紙カバーに、印刷されているイラストを文章で表現してみた。誰でも入りたくなりそうな、洋式トイレを想像してしまいそうである。どんな内容の一冊かと思ったら、介護スタッフ向けの書物だった。 「水タンクの表に背もたれがあり、赤色の便座シートが見える。両側には肘掛けオプションを設置、アヒルが便器の中でゆったりと泳ぎ、コメントには『トイレでスッキリ』と書き記している」。書籍の表紙カバーに、印刷されているイラストを文章で表現してみた。誰でも入りたくなりそうな、洋式トイレを想像してしまいそうである。どんな内容の一冊かと思ったら、介護スタッフ向けの書物だった。
 介護アドバイザーで「ケア・プロデュースRX組」代表、青山幸広先生の著書「おむつに頼らない、排泄介護術(雲母書房刊)」を、手にする機会に恵まれた。自分が「おむつだから」という単純な気持ちで、全頁数114ページをペラペラとめくる。「何をしたいのか、どこかへ行きたいのか、その人の胸の内を覗いてみよう」。文中にあった言葉に目を通すと、カラーマーカーペンでマーキングラインを引きたくなった。何も介護支援を必要とする人に限らず、ほかの人間だって理解の一歩がはじまる瞬間であろう。この基本には、初対面だとなかなか難しい。現場でも、意思疎通の単語を思い浮かぶ場面があるらしい。 介護アドバイザーで「ケア・プロデュースRX組」代表、青山幸広先生の著書「おむつに頼らない、排泄介護術(雲母書房刊)」を、手にする機会に恵まれた。自分が「おむつだから」という単純な気持ちで、全頁数114ページをペラペラとめくる。「何をしたいのか、どこかへ行きたいのか、その人の胸の内を覗いてみよう」。文中にあった言葉に目を通すと、カラーマーカーペンでマーキングラインを引きたくなった。何も介護支援を必要とする人に限らず、ほかの人間だって理解の一歩がはじまる瞬間であろう。この基本には、初対面だとなかなか難しい。現場でも、意思疎通の単語を思い浮かぶ場面があるらしい。
家族に恵まれた私には13年ほど前に建てた持ち家があるし、近所にいる支援してくれる方の信頼が厚く感謝に堪えない。反面、障害福祉の場合、出生時から高齢に至るまで一生、何らかのケアを受けていく。ある意味で一般社会に出ることもないまま、施設での生活を余儀なくされるケースも少なくない。本人が育ったところが施設だとすれば 、故郷や接してきた人は限られてしまうと思う。たとえば介護職員が、その人の思いを探っていくことは困難を極めていく。こうした状況で、高齢福祉にかかわらず、意思疎通の課題がある。対応策が浮かばなくて、職場を去っていく例が絶えない一方、前を向いて模索し続ける若手の存在があると聞く。福祉は共生へ一歩ずつ、前進していることは確かだ。 、故郷や接してきた人は限られてしまうと思う。たとえば介護職員が、その人の思いを探っていくことは困難を極めていく。こうした状況で、高齢福祉にかかわらず、意思疎通の課題がある。対応策が浮かばなくて、職場を去っていく例が絶えない一方、前を向いて模索し続ける若手の存在があると聞く。福祉は共生へ一歩ずつ、前進していることは確かだ。
事例①。介護施設で職員から嫌われる高齢女性Aさんについて、著書はこう書いている。「ベッドから起き上がろうともせず、毎日毎日横になった状態で、おむつにおしっこをしている。食事も寝床で済ませ、呼び鈴を押す様子はなく、私の話も聞く耳を持たない。気強さが見えるおばあさんの、気持ちをほぐすためには、こっちも辛抱強く接していこう」。チョコレートとヨーグルトが好きだという情報をつかみ、施設内の売店へ一緒に向かうチャンスがあり、そのとき青山先生(介護長)はトイレに行きたくなる。そんなきっかけが、おむつをしていたおばあさんにパンツを穿く、ポターブルトイレからお手洗い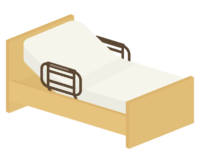 へ行く、普通の生活を取り戻そうと、気持ちに変化が見えくる。「これは驚いた。本当に、張本人なのか。介護長以外でも、このおばあさんは相手にしてくれる?」。多くの介護スタッフに稲妻のような衝撃が走り、改めて「人を知る」重要性を理解するに至った。「おばあさんがお手洗いに行って(青山先生がいる)隣の個室から(Aさんが)おしっこをする音が聞こえた。やればできる。介護する立場で達成感があり、一生忘れない『おしっこの音』となった」。青山先生の経験と知識を合わせた一例である。 へ行く、普通の生活を取り戻そうと、気持ちに変化が見えくる。「これは驚いた。本当に、張本人なのか。介護長以外でも、このおばあさんは相手にしてくれる?」。多くの介護スタッフに稲妻のような衝撃が走り、改めて「人を知る」重要性を理解するに至った。「おばあさんがお手洗いに行って(青山先生がいる)隣の個室から(Aさんが)おしっこをする音が聞こえた。やればできる。介護する立場で達成感があり、一生忘れない『おしっこの音』となった」。青山先生の経験と知識を合わせた一例である。
令和5年1月30日、セミナーの依頼があって、私の利用するショートスティ施設へ訪問した青山先生に、はじめてお目にかかる。「CDにある歌詞は、あなたが書いたのですか。心に響くような詞ですね。笑えそうな歌もあるね」。何気なく近づき、親しみやすく、気兼ねも見せずに話しかけてきて、少しびっくりした。続けてもう一言。「CDの残りがあったら友人にも聞かせたいので、青山に何枚か譲ってくれませんか」。そのあと、ひとり風呂の介助やベッドから電動車いすへ移乗時の動作で、スタッフとともに指導を受けた。自分の手落ちで、まだCDを渡す約束は果たせていない。
事例②。「死んだおじいちゃんの墓参りに行きたい」。高齢女性Bさんは、慢性関節リウマチを患い、両足が棒のように伸びていて、ちょっと身体 を動かすと「痛い、痛い」の連発。おむつをはじめ、ベッドで一日中寝たきりの暮らしをしている。「霊園はどこですか」と尋ねたところ、Bさんが「四国の松山だよ」の返事がきた。現在地は青森市にある施設のため、行くとしたら飛行機を利用するかしない。「口走りに連れて行ってあげるよと約束した。困ったなぁ」。青山先生は必死に考える。おむつ交換をどこでやるか、どうするのという質問にプラス極めつきの切り札に「おしっこが分かりますか」と、Bさんに答えを出してもらう。ブーメランみたいに一発、一言「尿意は分かります」。これがきっかけになって、Bさんの介護計画がスタートした。「ベッドから起きてポターブルトイレに座る→ポターブルトイレからベッドへ移る」。何度も同じ動作を繰り返すうちに、介護職員が簡単に(Bさんを)ポターブルトイレまで移動できるようになった。トレーニングに耐えてBさんは以前よりも、身体状態がよくなる。「尿意・便意が分かる、できるだけ自宅生活を取り戻したい」。利用者のその気持ちを汲み、役に立とうするのが我々の仕事だと、Bさんに接しながら、はじめて青山先生は学び得たと話す。 を動かすと「痛い、痛い」の連発。おむつをはじめ、ベッドで一日中寝たきりの暮らしをしている。「霊園はどこですか」と尋ねたところ、Bさんが「四国の松山だよ」の返事がきた。現在地は青森市にある施設のため、行くとしたら飛行機を利用するかしない。「口走りに連れて行ってあげるよと約束した。困ったなぁ」。青山先生は必死に考える。おむつ交換をどこでやるか、どうするのという質問にプラス極めつきの切り札に「おしっこが分かりますか」と、Bさんに答えを出してもらう。ブーメランみたいに一発、一言「尿意は分かります」。これがきっかけになって、Bさんの介護計画がスタートした。「ベッドから起きてポターブルトイレに座る→ポターブルトイレからベッドへ移る」。何度も同じ動作を繰り返すうちに、介護職員が簡単に(Bさんを)ポターブルトイレまで移動できるようになった。トレーニングに耐えてBさんは以前よりも、身体状態がよくなる。「尿意・便意が分かる、できるだけ自宅生活を取り戻したい」。利用者のその気持ちを汲み、役に立とうするのが我々の仕事だと、Bさんに接しながら、はじめて青山先生は学び得たと話す。
2024年、立春過ぎとはいえまだ寒い日、いつもの施設で丸1年ぶりに青山先生と再会ができた。ひとり部屋でテレビを見ていたら、親しみやすい顔がこちらへ眼(まなこ)を向ける。何から話そうかと迷った。が、この前の質問「やりたいことは何かありますか」。とか、テレビ映像をヒントに使う。一方で、事例②のBさんが頭に浮かび、話す内容が固まる。「この歳になるまで、飛行機に乗って旅をしたいことがないです」。私の話は、青山先生の耳に届いたと思う。
養護学校から地元小学校へ転校した3年生のとき、教室に貼ってあった日本地図で最北の島、北海道に興味を引く。人の横顔みたいな島の形が面白くて、広告紙の裏面を使い、北海道の地図をまねして書いた。一時は島と心の距離が遠くなったけれど、再熱したのは高校生になってからだ。ハンディトランシバーを持った ら、思いを寄せていた島の知らない人と、アマチュア無線で交信ができた。思わず、胸が高まる。好物の麺類なら、サッポロ味噌ラーメンが恋しくてたまらなかった。現実を見ると私の場合は、事例②のBさんとケア環境で重ね合わせてしまいがち。参ったな。さてどうしよう。 ら、思いを寄せていた島の知らない人と、アマチュア無線で交信ができた。思わず、胸が高まる。好物の麺類なら、サッポロ味噌ラーメンが恋しくてたまらなかった。現実を見ると私の場合は、事例②のBさんとケア環境で重ね合わせてしまいがち。参ったな。さてどうしよう。
やりたいことはまだある。病院生活を過ごしてきた4年前から、パソコンを使い書き溜めている日記や作文を、一つにまとめたいという夢を持つ。自分の墓場へ持参するのではなく、広範囲に公開したいと考えている。どういう形で発表に持っていくか模索中だ。ネットを利用した方法が、もっとも手軽であろう。望むところは、見知らぬ人々まで一冊ずつ手にしてもらいたい思いが強い。自費か、企画出版のどちらかで決めたい。まずは今年暮れまで、毎月の作文書きに励み、公衆の場で読まれるような内容に整えていく。青山先生にはスタートの段階から、指導並びに支援をいただきたいと思っている。
著書にはこのほか、排泄介護をプロの視線で、実践写真 をふんだんに使いより分かりやすく解説する、現場で働く人たち向けの「必至本」だ。青山先生には、まだ多数の関係著書がある。あくまでも今回は感想文のつもりで、一つの高著を紹介してみた。介護分野も奥が深く、当たり前の生活を支援する難しさがあることを知る。最後に、青山先生の今後の活動を祈念するとともに、介護エキスパートの養成がさらに進むよう願ってやまない。 をふんだんに使いより分かりやすく解説する、現場で働く人たち向けの「必至本」だ。青山先生には、まだ多数の関係著書がある。あくまでも今回は感想文のつもりで、一つの高著を紹介してみた。介護分野も奥が深く、当たり前の生活を支援する難しさがあることを知る。最後に、青山先生の今後の活動を祈念するとともに、介護エキスパートの養成がさらに進むよう願ってやまない。
2024/03/30
|