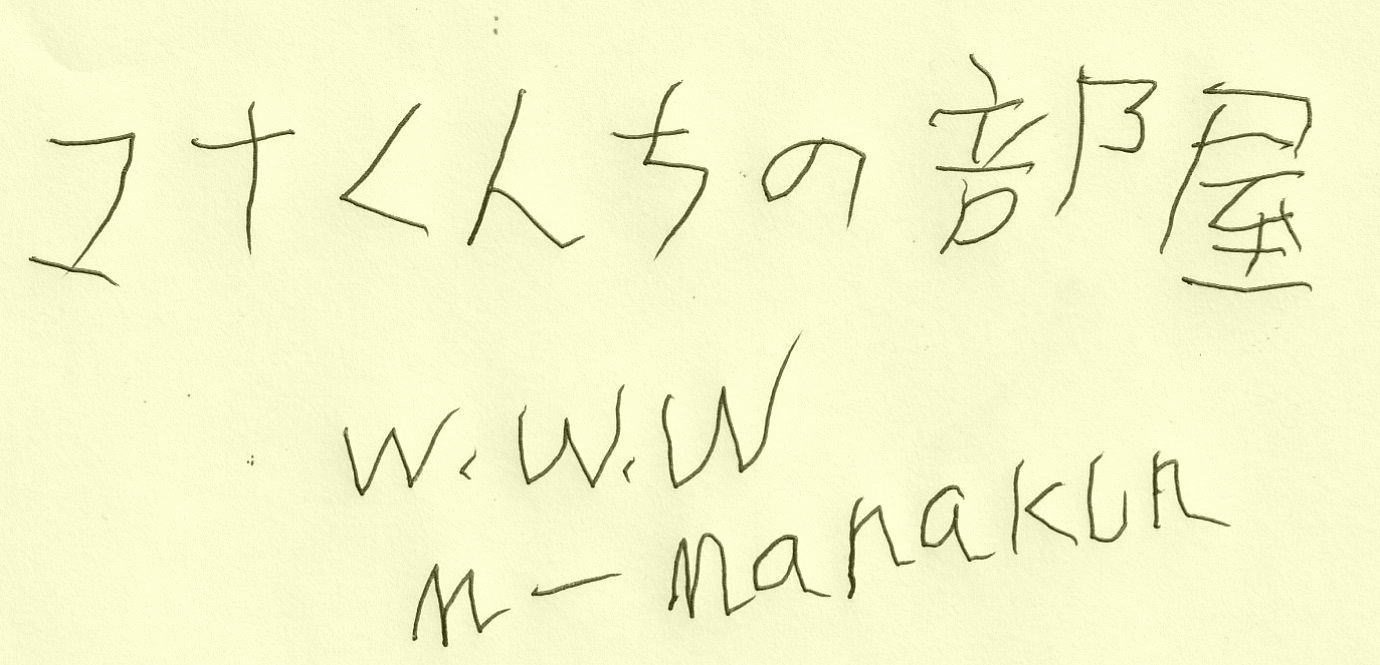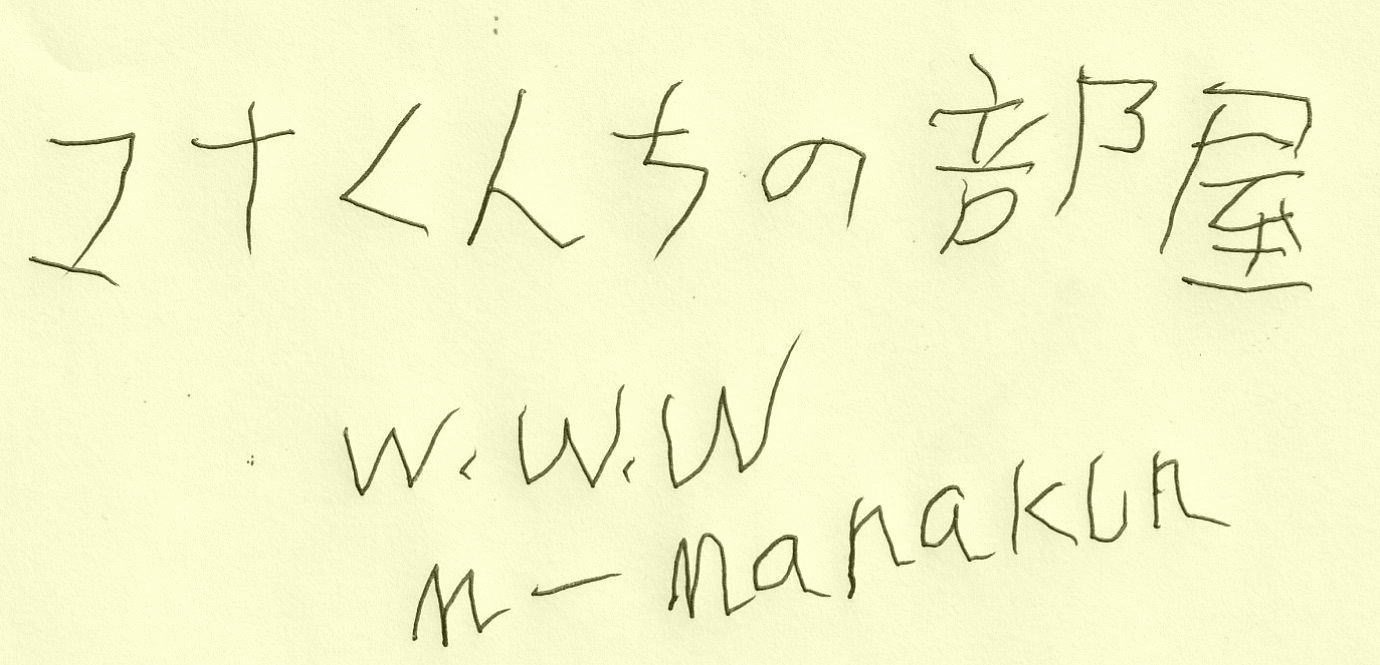|
 若いころ、面白半分に半信半疑で頭に浮かんでいた。「きょうぼくむら」という、実際にはない言葉。「むら」を削除し「きょうぼく」をネットで調べてみると、丈の高い木を指し、例として樫、松、杉がそれに当てはまる。日常では「樹」と示すのが一般的だと分かった。いわば、たくましい喬木(きょうぼく)である。自分が生まれ育ったところは、天竜川の東側、河岸段丘の一帯で、伊那山脈、南アルプスを眺められ、飯田市と高森町、豊丘村に隣接する総人口5,684人(2024年1月1日)の地方公共団体。明治のはじめ、すでに5村からなる、いまの村落が誕生していた。歴史の長さも、ひときわ名高い。住所は大字がなく番地のみであり、一見、どこの地区か分かりにくい。旧集落ごとの郵便番号は便利だが、一つに統一した番号も存在するため、どちらを選ぶか戸惑うケースもあろう。 若いころ、面白半分に半信半疑で頭に浮かんでいた。「きょうぼくむら」という、実際にはない言葉。「むら」を削除し「きょうぼく」をネットで調べてみると、丈の高い木を指し、例として樫、松、杉がそれに当てはまる。日常では「樹」と示すのが一般的だと分かった。いわば、たくましい喬木(きょうぼく)である。自分が生まれ育ったところは、天竜川の東側、河岸段丘の一帯で、伊那山脈、南アルプスを眺められ、飯田市と高森町、豊丘村に隣接する総人口5,684人(2024年1月1日)の地方公共団体。明治のはじめ、すでに5村からなる、いまの村落が誕生していた。歴史の長さも、ひときわ名高い。住所は大字がなく番地のみであり、一見、どこの地区か分かりにくい。旧集落ごとの郵便番号は便利だが、一つに統一した番号も存在するため、どちらを選ぶか戸惑うケースもあろう。
 鹿児島県立図書館長を務めた小説家で、児童文学家の椋鳩十(本名・久保田彦穂)は、名誉村民第1号となった。主に、子どもたちに親しまれる作品を生んだ。相撲界を見ると、戦前から活躍した、関脇・高登のちの大山親方(本名・吉川渉)が出てくる。力士生活では、目立った成績は残っていないが、仲間同士の信頼が厚く、乱れていた大日本相撲協会(春秋園事件)の再生に全力を尽くす。引退後、新しい部屋を設立し弟子(大関・松登)を育てる。NHK相撲解説者でも人気を集める、国民的なヒーローだった。ほかにも、各界で功績を収めたみなさんを忘れてはなるまい。 鹿児島県立図書館長を務めた小説家で、児童文学家の椋鳩十(本名・久保田彦穂)は、名誉村民第1号となった。主に、子どもたちに親しまれる作品を生んだ。相撲界を見ると、戦前から活躍した、関脇・高登のちの大山親方(本名・吉川渉)が出てくる。力士生活では、目立った成績は残っていないが、仲間同士の信頼が厚く、乱れていた大日本相撲協会(春秋園事件)の再生に全力を尽くす。引退後、新しい部屋を設立し弟子(大関・松登)を育てる。NHK相撲解説者でも人気を集める、国民的なヒーローだった。ほかにも、各界で功績を収めたみなさんを忘れてはなるまい。
令和6年,新春。毎週日曜日の午後、70代の女性・Dさんがやってくる。顔を合わせると、まず質問あ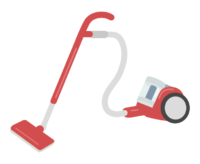 り…。「きょうは何をしますか」。普段着姿のDさんは、エプロンさえしてはいないが、屋内の掃除を依頼すると、快く引き受けてくれる。床に電気掃除機をかけ、つぎにモップ使用で仕上げは完了。窓を開けて換気にも気遣うが、最近は新しいエアコンを見るなり控えめになった。「ここで、一服いかが」となるはずだけど、自分ではお茶の用意ができない。「心配ご無用」とささやくみたいに、荷物からお茶が入った水筒を持ち、グッと飲み干すDさん。わが家をあとにするときは、ゴミ出しを必ずしていく。まさしく、訪問介護の助手役を見事に務めている。 り…。「きょうは何をしますか」。普段着姿のDさんは、エプロンさえしてはいないが、屋内の掃除を依頼すると、快く引き受けてくれる。床に電気掃除機をかけ、つぎにモップ使用で仕上げは完了。窓を開けて換気にも気遣うが、最近は新しいエアコンを見るなり控えめになった。「ここで、一服いかが」となるはずだけど、自分ではお茶の用意ができない。「心配ご無用」とささやくみたいに、荷物からお茶が入った水筒を持ち、グッと飲み干すDさん。わが家をあとにするときは、ゴミ出しを必ずしていく。まさしく、訪問介護の助手役を見事に務めている。
 5・6年前、村役場からお知らせが届き、A4サイズの用紙を手にした。「あなたも私も、おたすけ隊、たかぎレンジャーに入りませんか」。こんな見出しが躍っていて、説明文章にはこうであったように思う。「少し手助けをしてほしい人(利用者)、何かしたいと思っている人(協力者)をつないで、住民の相互の支え合いにより、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指す…(抜粋)」。行政サービスだけに頼らない、ボランティア的な取り組みを推進する事業と受け止める。だが、自分には理解し難い部分があった。ずっと前から、関係者のあいだで、折り合いのない論議が繰り返されている。それは「ボランティアは、有償か無償か」だ。自発・自主性に自ら行動するのが社会奉仕員であって、利益を求めない考えが本筋ではないかと思う。支援を受ける側は、相手の善意を謙虚に受け止め、お互いの関係に感謝の気持ちを示すことが必要。ここから先に謝礼というか、金銭的な展開が生まれるような感じする。前者が正なら負の後者はどうなのか。(有償の方が)気遣いはない、高齢者にも分かりやすい、支援者を選ばない。そうしたメリットが、おたすけ隊の趣旨と一致しやすいと考える。 5・6年前、村役場からお知らせが届き、A4サイズの用紙を手にした。「あなたも私も、おたすけ隊、たかぎレンジャーに入りませんか」。こんな見出しが躍っていて、説明文章にはこうであったように思う。「少し手助けをしてほしい人(利用者)、何かしたいと思っている人(協力者)をつないで、住民の相互の支え合いにより、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指す…(抜粋)」。行政サービスだけに頼らない、ボランティア的な取り組みを推進する事業と受け止める。だが、自分には理解し難い部分があった。ずっと前から、関係者のあいだで、折り合いのない論議が繰り返されている。それは「ボランティアは、有償か無償か」だ。自発・自主性に自ら行動するのが社会奉仕員であって、利益を求めない考えが本筋ではないかと思う。支援を受ける側は、相手の善意を謙虚に受け止め、お互いの関係に感謝の気持ちを示すことが必要。ここから先に謝礼というか、金銭的な展開が生まれるような感じする。前者が正なら負の後者はどうなのか。(有償の方が)気遣いはない、高齢者にも分かりやすい、支援者を選ばない。そうしたメリットが、おたすけ隊の趣旨と一致しやすいと考える。
 平成24年、村の社会福祉協議会職員だったDさんは、訪問介護の主任として活躍していた。教員のご主人、お子さんファミリーで二世帯住宅に住む。お嫁さんが働く決意をしたので、主婦に転身することを余儀なくされた。いまなお「孫育て」に専念している。近ごろは、ご家庭のことを聞いていないし、話してもくれないが、すべて円満に進んでいるはず。傍らで、隣村の介護施設相談役を引き受けるなど、広く社会奉仕活動に参加してもいる。ネット検索で今回は、愛知県豊橋市の活動にたまたまヒットした。全国エリアで行われているおたすけ隊のほかに、個性的な取り組みが紹介されている。分かりやすく簡単な式を表すと、こんな感じではないか。「支援を求めている側+人のために何かしたいと考える側=支え合い地域」。踏み込んでいくと、そのための活動は「訪問タイプ(おたすけ隊等)」と「通いのタイプ(コミュニティカフェ等)」に分けられ、お互いさまの精神をもって、さらに地域福祉の充実を図ろうとする啓発運動だと思う。 平成24年、村の社会福祉協議会職員だったDさんは、訪問介護の主任として活躍していた。教員のご主人、お子さんファミリーで二世帯住宅に住む。お嫁さんが働く決意をしたので、主婦に転身することを余儀なくされた。いまなお「孫育て」に専念している。近ごろは、ご家庭のことを聞いていないし、話してもくれないが、すべて円満に進んでいるはず。傍らで、隣村の介護施設相談役を引き受けるなど、広く社会奉仕活動に参加してもいる。ネット検索で今回は、愛知県豊橋市の活動にたまたまヒットした。全国エリアで行われているおたすけ隊のほかに、個性的な取り組みが紹介されている。分かりやすく簡単な式を表すと、こんな感じではないか。「支援を求めている側+人のために何かしたいと考える側=支え合い地域」。踏み込んでいくと、そのための活動は「訪問タイプ(おたすけ隊等)」と「通いのタイプ(コミュニティカフェ等)」に分けられ、お互いさまの精神をもって、さらに地域福祉の充実を図ろうとする啓発運動だと思う。
昨年の暮れ、認知機能障害がある母親をサポートしている、すぐ近く住む2つ年上の女性に、パソコンとインクジェットプリンターを使い年賀状印刷をす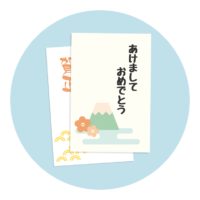 るため、お手伝いを頼む。いつでもプリントができるように準備をして、彼女がくるのを待つ。年賀はがきをプリンターにセットしてもらい、印刷済みのはがきを仕分ける作業もお願いする。生まれつきの障害に加え、左上下肢まひが起こるまでは、自分ですべてやっていたが、プリントアウトを人に依頼するのははじめだった。タクスが順調に進み、お互いに胸をなでおろす。年が明けて2月の中旬、お世話になったお礼に心ばかりの気持ちを渡した。「今後、心配はしないでほしい」と、釘を打たれる。彼女の場合、これ以上の口出しは無用だと感じた。近所同士何かと世話になる、少しでも力になれればそれでいい。社会奉仕の原点に顧みた思いであった。 るため、お手伝いを頼む。いつでもプリントができるように準備をして、彼女がくるのを待つ。年賀はがきをプリンターにセットしてもらい、印刷済みのはがきを仕分ける作業もお願いする。生まれつきの障害に加え、左上下肢まひが起こるまでは、自分ですべてやっていたが、プリントアウトを人に依頼するのははじめだった。タクスが順調に進み、お互いに胸をなでおろす。年が明けて2月の中旬、お世話になったお礼に心ばかりの気持ちを渡した。「今後、心配はしないでほしい」と、釘を打たれる。彼女の場合、これ以上の口出しは無用だと感じた。近所同士何かと世話になる、少しでも力になれればそれでいい。社会奉仕の原点に顧みた思いであった。
おたすけ隊としてわが家へ訪問するDさんには、請求のあった利用料を支払いしている。つい雑になりやすいという、友人や遠い親戚を名乗るCさんも、事前に決めたサポート代を受けとる中で、信金・JAで現金を下ろすときや、松本市や近くの医療機関を受診する際、いつも同行を惜しまない助っ人マン。メール交換が絶えず、その分、お互いの性格を認めた間柄になりつつある。家にラーメンの材料を持ってきて、得意の腕前を披露してくれる先生は、夫婦で塾を経営している。それぞれに方向や立場が違っても、私を支えることに何ら変わりはない。
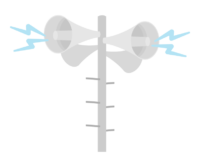 今回紹介した、支える側のメンバーを大切にして、行政サービスで賄えないとき、頼りになる人たちも新たに見つけられたら、この上はない。そのためには、薄れてきている地域へ出ていき、喬木村のみなさんと触れ合う機会を持つしかないと痛感する、このごろだ。 今回紹介した、支える側のメンバーを大切にして、行政サービスで賄えないとき、頼りになる人たちも新たに見つけられたら、この上はない。そのためには、薄れてきている地域へ出ていき、喬木村のみなさんと触れ合う機会を持つしかないと痛感する、このごろだ。
2024/02/27
|