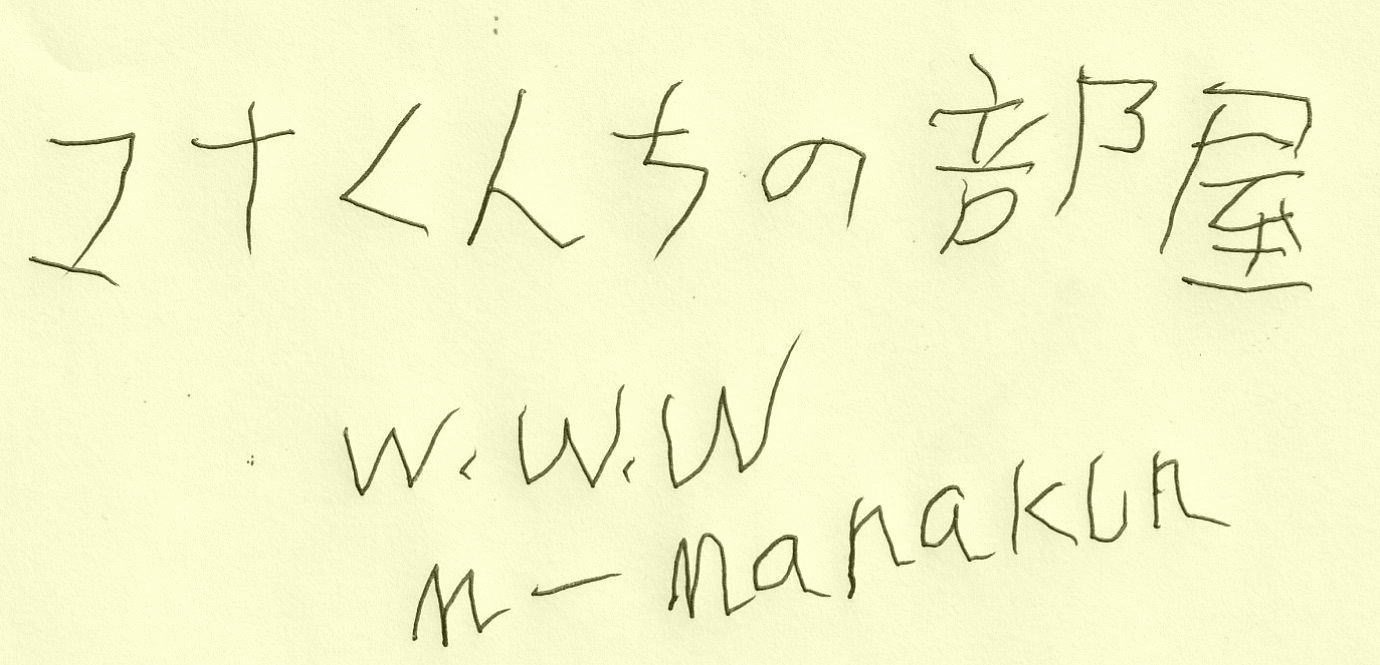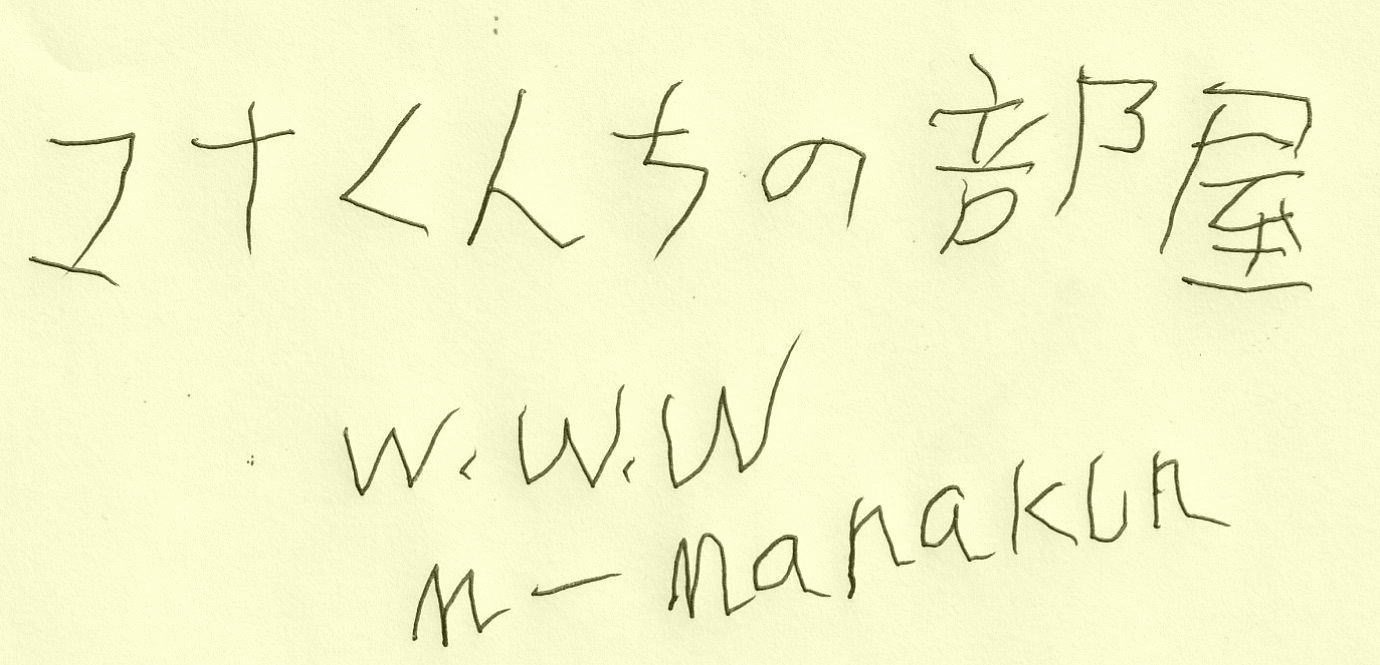|
 「嫌なできごとやつらいことを思い出した。これはもしかしたら、本能の仕業ではないか…?」。地方紙の投稿欄、テーマ「新年に思う」で、定年を過ぎもうすぐ1年が経つという、元教員の文章に目が止まった。教育現場で数多くの楽しい思い出をつくったと語るが、嫌でつらいことばかりが頭に浮かび悩んだらしい。自分での解決が必要だと考えた末、生き物の本能に注目する。生き物にとってつらく嫌なことは、天敵に襲われる一面で、決して忘れてはいけない。命にかかわると警戒が必要。楽しかった経験も大切にしていく。この謎を解き式が、気持ちを楽にさせたという。元教員は、プラス思考を求めていたのだろうか。令和6年辰年のはじめに際し、自分の抱負に触れてみた。 「嫌なできごとやつらいことを思い出した。これはもしかしたら、本能の仕業ではないか…?」。地方紙の投稿欄、テーマ「新年に思う」で、定年を過ぎもうすぐ1年が経つという、元教員の文章に目が止まった。教育現場で数多くの楽しい思い出をつくったと語るが、嫌でつらいことばかりが頭に浮かび悩んだらしい。自分での解決が必要だと考えた末、生き物の本能に注目する。生き物にとってつらく嫌なことは、天敵に襲われる一面で、決して忘れてはいけない。命にかかわると警戒が必要。楽しかった経験も大切にしていく。この謎を解き式が、気持ちを楽にさせたという。元教員は、プラス思考を求めていたのだろうか。令和6年辰年のはじめに際し、自分の抱負に触れてみた。
父を尊敬していたから母と2人暮らしになると、ちょっとしたことで口げんかをした。どちらも、もめごとはたまったものではない。あるとき、母のメモ書きに胸を打つ。「いつも怒ってしまい、ごめんなさい。こんな状態 じゃあ、お互い疲れるよね。母は、プラス思考でリラックスしています。学(お前)も試してみては…?」。いまでは、人に頼らなくてはならない自分には、絶えず思う言葉は「きっと、うまくいく。なんとかなる」である。逆の表現は、マイナス思考か。「自分には無理。必ず失敗する。上手にいくはずがない」。どう考えても、消極的なものの見方となる。笑ったりする表向きの人には、共感しにくいかもしれない。しかし、人の心はデリケートな感じがする。過去は積極的な行動をとっていながら、体調がすぐれないなど、何かの衝撃を受けてしまい、それがもとで気持ちが変わるケースもあると思う。要するに、周囲からの影響を受けない、強い心を維持するには忍耐力が欠かせないだろう。 じゃあ、お互い疲れるよね。母は、プラス思考でリラックスしています。学(お前)も試してみては…?」。いまでは、人に頼らなくてはならない自分には、絶えず思う言葉は「きっと、うまくいく。なんとかなる」である。逆の表現は、マイナス思考か。「自分には無理。必ず失敗する。上手にいくはずがない」。どう考えても、消極的なものの見方となる。笑ったりする表向きの人には、共感しにくいかもしれない。しかし、人の心はデリケートな感じがする。過去は積極的な行動をとっていながら、体調がすぐれないなど、何かの衝撃を受けてしまい、それがもとで気持ちが変わるケースもあると思う。要するに、周囲からの影響を受けない、強い心を維持するには忍耐力が欠かせないだろう。
 母は40代で乳がん手術を経験し、そのあとは元気で農家の妻として、稲作や養蚕業に励む。もっとも、旅館の娘だったから農業はきつかったと思う。父が他界して半年後に、声がかすれと言い出す。「早めに総合病院で診てもらった方がいいよ」と、診察を勧めた。形成外科から耳鼻咽喉外科へ回されると、意外な診断が待っていた。診察室から出てきた、母の表情は重苦しいように見えた。乳がんを患ってから40年近く過ぎても、がん遺伝子はどこかに潜んでいたのか。「声が出ない」。ショッキングな医師の説明には、親子ともども言葉を失う。決断に時間は要らなかった。「これからも一緒 母は40代で乳がん手術を経験し、そのあとは元気で農家の妻として、稲作や養蚕業に励む。もっとも、旅館の娘だったから農業はきつかったと思う。父が他界して半年後に、声がかすれと言い出す。「早めに総合病院で診てもらった方がいいよ」と、診察を勧めた。形成外科から耳鼻咽喉外科へ回されると、意外な診断が待っていた。診察室から出てきた、母の表情は重苦しいように見えた。乳がんを患ってから40年近く過ぎても、がん遺伝子はどこかに潜んでいたのか。「声が出ない」。ショッキングな医師の説明には、親子ともども言葉を失う。決断に時間は要らなかった。「これからも一緒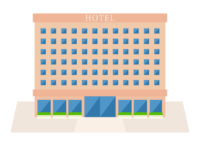 に暮らしたい。母に元気でいてほしい」。急に、この思いが込み上げてくる。喉頭がんと告知した医師からは、生きるための手術を受けるように、と言われる。声帯を切除すると発声ができない。相手とのコミュニケーション手段が課題となる。そこで、母が選んだ方法はメモ書きであった。冬場は若いころから、実家で電話番などの手伝いしていて、メモを取ることが多く、この応用を会話に生かす。すらすらとペンを滑らせる速さには、普通の会話と何ら変わりはないように感じた。 に暮らしたい。母に元気でいてほしい」。急に、この思いが込み上げてくる。喉頭がんと告知した医師からは、生きるための手術を受けるように、と言われる。声帯を切除すると発声ができない。相手とのコミュニケーション手段が課題となる。そこで、母が選んだ方法はメモ書きであった。冬場は若いころから、実家で電話番などの手伝いしていて、メモを取ることが多く、この応用を会話に生かす。すらすらとペンを滑らせる速さには、普通の会話と何ら変わりはないように感じた。
8時間の手術が、無事に終わる。療養期間から、自己発声練習も怠らない母だった。マイクのような一握りの増幅器をのどに当てると、枯れたような小さな声が聞こえる。「私がしゃべっているのに分からないのか?」。耳が遠い息子を気遣ってくれた。声帯がないけど、人体の再生力には驚く。話をする相手によって、メモ書きか、自己発声かを選んでいた母であった。ある医療関係ホームページに、こう書いている。「喉頭全摘出術を受けた場合は、呼吸をするために首に開けた穴(永久気管孔)を清潔に保ち、乾燥させないケアが必要です(抜粋)」。もう一つのネック、気道切開のため、衛生ケアがつきものとなった。手術を受けた時点で、身体障害者手帳3級が交付される。国・役場から支給される日常生活用具で、吸入器(ネブライザー)を使用しての毎日が続く。食事は普通食となる。いままでとは違う過酷な生活には 、母の横にいるだけの自分に情けなく思った。原因とリスクは、飲酒・たばこの常例者に多く見られるらしい。想像であるが、男性が罹患する確率が高いといえよう。喉頭全摘出術をした人の全国組織があり、母も長野県支部に籍を置く。南信地域の仲間とともに、情報交換や発声練習に没頭していた。会員同士の家族と、新、忘年会のほか、ちょっとした旅が組まれ、自分も参加させてもらう。みなさん、明るい雰囲気をつくっていて悲壮感を垣間見た。県支部の女性会員は、母も含め2人乃至3人だったと思う。 、母の横にいるだけの自分に情けなく思った。原因とリスクは、飲酒・たばこの常例者に多く見られるらしい。想像であるが、男性が罹患する確率が高いといえよう。喉頭全摘出術をした人の全国組織があり、母も長野県支部に籍を置く。南信地域の仲間とともに、情報交換や発声練習に没頭していた。会員同士の家族と、新、忘年会のほか、ちょっとした旅が組まれ、自分も参加させてもらう。みなさん、明るい雰囲気をつくっていて悲壮感を垣間見た。県支部の女性会員は、母も含め2人乃至3人だったと思う。
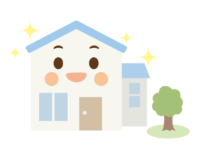 2012年の春。よくよく考えた。この家は、エアコンはないし台所も43年前(当時)に、父が増改築したままだ。自分にできることがあるとすれば、親子で快適な暮らしがある、そんな自宅にしたいと思いつく。「そうだね」。母は笑みを浮かべ、うれしそうにこちらの提案を飲み込んでいた。早速、業者に来てもらい話を進める。「しっかりとしたお家ですね。リフォームをご希望のことですが、2階まで続く通し柱が何本もあるため、間取りが思うようならないのです」。築後140年余りの建築物を、ありのままに評価した業者は、わが家をあとに姿を消す。再び母に尋ね了解を得る。「家の前に別宅を建てたい」。同じ業者を交えて、迷いのない気持ちを伝える。お金は必要となるが、親孝行をしたかった。段差を解消した屋内、横引きドアにノブ付、全室エアコンありの別宅。その年の暮れ、夢のような新築が完成。本宅から引っ越しすると、元気な母の笑顔を見た。 2012年の春。よくよく考えた。この家は、エアコンはないし台所も43年前(当時)に、父が増改築したままだ。自分にできることがあるとすれば、親子で快適な暮らしがある、そんな自宅にしたいと思いつく。「そうだね」。母は笑みを浮かべ、うれしそうにこちらの提案を飲み込んでいた。早速、業者に来てもらい話を進める。「しっかりとしたお家ですね。リフォームをご希望のことですが、2階まで続く通し柱が何本もあるため、間取りが思うようならないのです」。築後140年余りの建築物を、ありのままに評価した業者は、わが家をあとに姿を消す。再び母に尋ね了解を得る。「家の前に別宅を建てたい」。同じ業者を交えて、迷いのない気持ちを伝える。お金は必要となるが、親孝行をしたかった。段差を解消した屋内、横引きドアにノブ付、全室エアコンありの別宅。その年の暮れ、夢のような新築が完成。本宅から引っ越しすると、元気な母の笑顔を見た。
月日は流れ、お互いに年齢を重ね合う。そこには別宅がどっしりと構え、2人の身体の衰えをサポートしてくれた。がん遺伝子と戦ってきたが、追い打ちをかけように循環器内科へ行く回数が増す。先天性心疾患があり、弁膜症を悪化させていた。医師は断言する。「あなたは大きな手術 していて、さらに心疾患が心配です。身体に負担がかからないカテーテル治療(冠動脈バイパス術)を、諏訪日赤で受けてください」。遠方先の入院、治療に戸惑う母に、納得させる思案は浮かばなかった。病状は進み、心血管外科へと足が向く。ここの医師は、CT画像を見ながら「これなら大丈夫です。開胸をしますが、手術傷は10センチくらいです。大動脈弁置換術ですので、人工弁を取りつけます」と解説する。藁にもすがる思いで聞き入る親子。地元で入院して手術が可能。「循環器内科とも、連絡を取り合っていきます」と、心血管外科医はつけ加えた。同じ病院だったので、複雑な心境であったことは確か。手術を受ける本人が、意思を決める瞬間となった。 していて、さらに心疾患が心配です。身体に負担がかからないカテーテル治療(冠動脈バイパス術)を、諏訪日赤で受けてください」。遠方先の入院、治療に戸惑う母に、納得させる思案は浮かばなかった。病状は進み、心血管外科へと足が向く。ここの医師は、CT画像を見ながら「これなら大丈夫です。開胸をしますが、手術傷は10センチくらいです。大動脈弁置換術ですので、人工弁を取りつけます」と解説する。藁にもすがる思いで聞き入る親子。地元で入院して手術が可能。「循環器内科とも、連絡を取り合っていきます」と、心血管外科医はつけ加えた。同じ病院だったので、複雑な心境であったことは確か。手術を受ける本人が、意思を決める瞬間となった。
3回目の大手術も成功裏に終わる。しかしながら、心不全、狭心症、胸水の症状が、頻繁にみられるようになってしまった。自分に問いかけてみる。「人工弁にしたのは何のためだったか」。答えは一つ、母の身体の衰えだ。あとは、生命力を信じていくしかないと思った。「お母さん、がんばってね。僕は家を守っているよ」。日々に迫る寂しさの中、とにかく元気づけに徹する。私たち2人を温かく見守ってくれた、まわりの皆様に感謝をしたい。
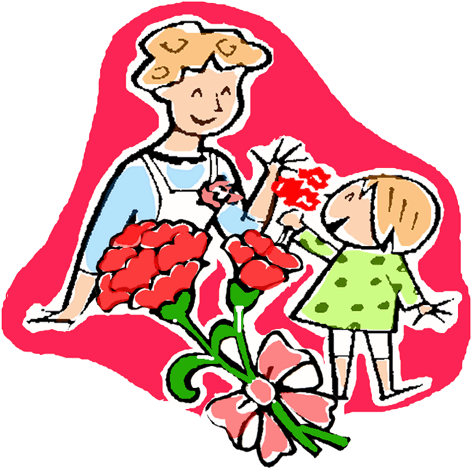 2020年の春、彼岸過ぎに、穏やかな表情の母が別宅へ戻ってきた。父方も併せて、親戚の方々が駆けつけてくる。もう、病院へ行く気もなさそう。自分のハートの中で、元気になった母がいる。これは、プラス思考の表れと確信すると同時に、嫌なこと、つらい思い出でも大切にしていくという、自分の余生のスタートであろう。これからもずっと、心に刻みたい一言がある。「母はいつも別宅で暮らしいて、息子の顔を見たいと思っている」のだと…。ありふれた今年の抱負となった。 2020年の春、彼岸過ぎに、穏やかな表情の母が別宅へ戻ってきた。父方も併せて、親戚の方々が駆けつけてくる。もう、病院へ行く気もなさそう。自分のハートの中で、元気になった母がいる。これは、プラス思考の表れと確信すると同時に、嫌なこと、つらい思い出でも大切にしていくという、自分の余生のスタートであろう。これからもずっと、心に刻みたい一言がある。「母はいつも別宅で暮らしいて、息子の顔を見たいと思っている」のだと…。ありふれた今年の抱負となった。
2024/02/05
|