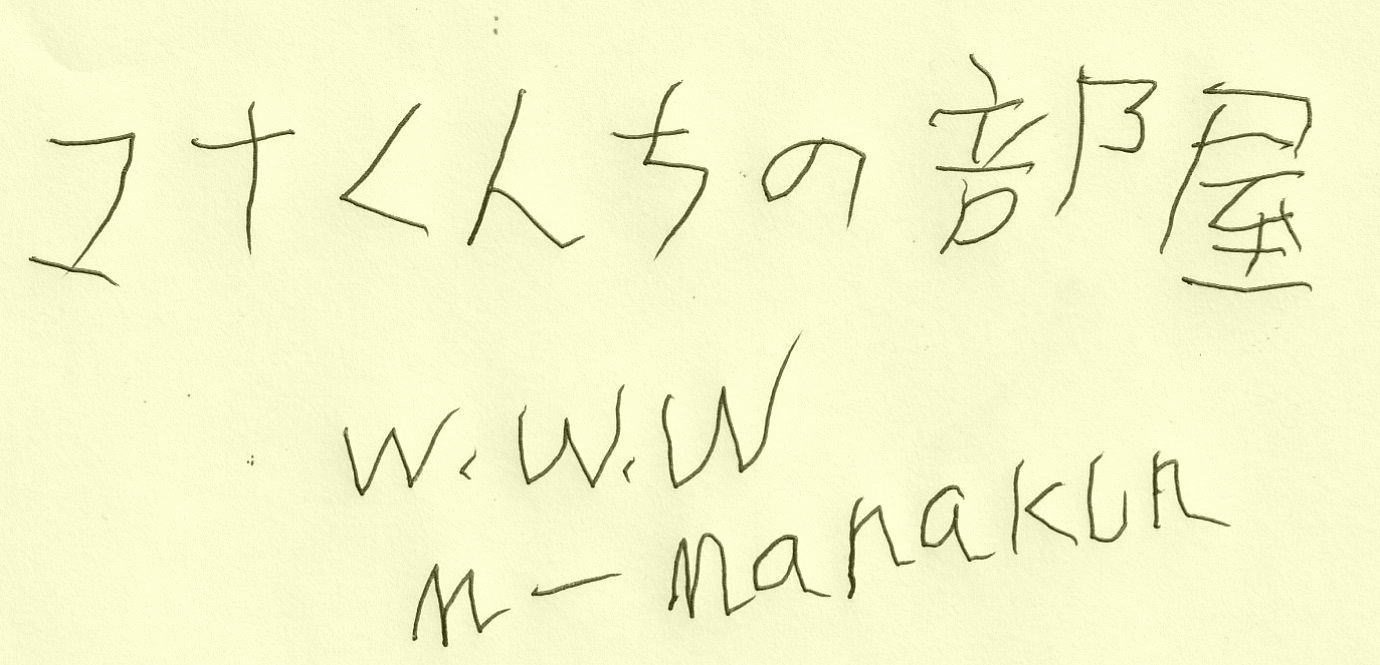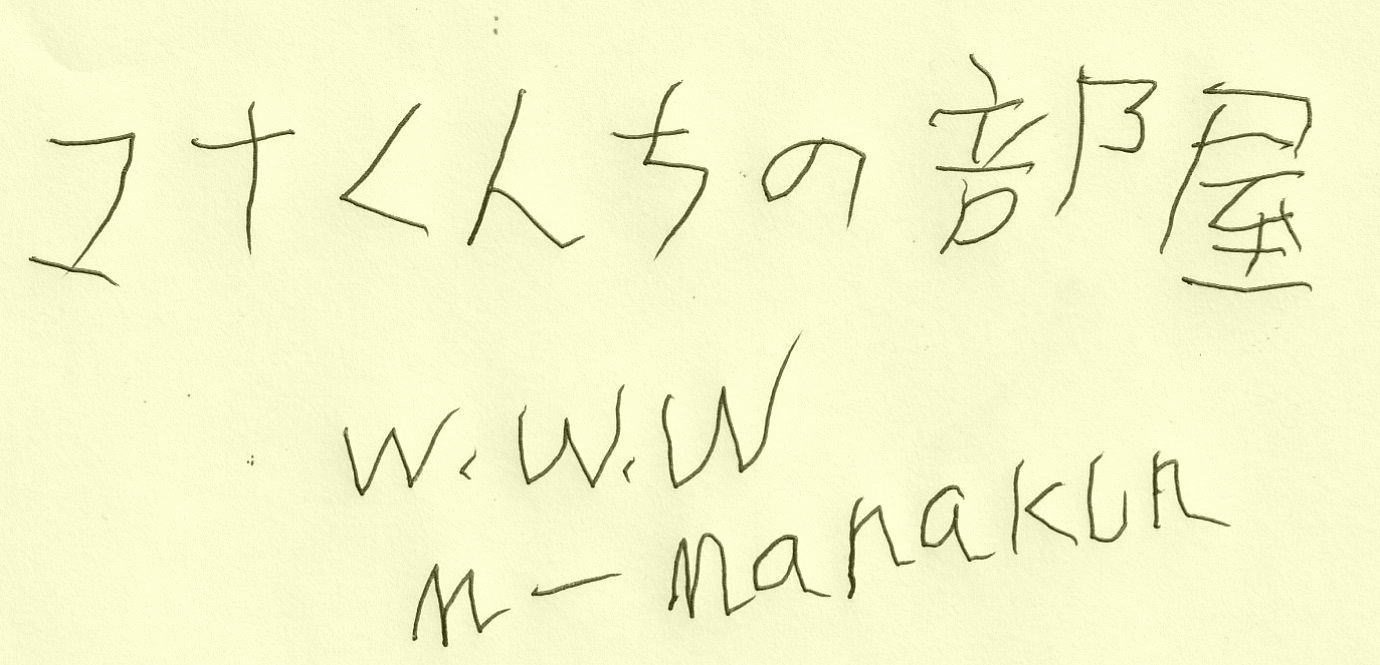|
人は疑われることがある。「私はそんなことは知らない」。張本人は否定する。相手から疑われたら、正直に話せばよいだろう。家族や友だちなど身近な人とであれば、ハテナ(?)解消が早そうだ。どうやら解決の糸口となるのは、疑われている人物の心を知っているかがポイントとなりそうな気がする。こんな話は日常茶飯ごととも言える。だが、社会集団の中では疑われると怖くな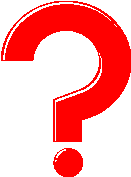 ってしまう。なぜだろうか。司法世界は私には無知であるが、一人の国民の立場で考えてみたい。その一例として、裁判での有罪と無罪の判断が正しいかであろう。もしも、事実隠しがあるならば、少数であってもえん罪を生む可能性がある。有罪となる場合が多数の中で、長期期間にわたり刑を受けながら無実が明らかになるとしたら、それは法の罪といってよいか。 ってしまう。なぜだろうか。司法世界は私には無知であるが、一人の国民の立場で考えてみたい。その一例として、裁判での有罪と無罪の判断が正しいかであろう。もしも、事実隠しがあるならば、少数であってもえん罪を生む可能性がある。有罪となる場合が多数の中で、長期期間にわたり刑を受けながら無実が明らかになるとしたら、それは法の罪といってよいか。
全国の病院で医療ミスが後を絶たない現実の中、呼吸器外し事件も発覚している。その一つ、2003年5月滋賀県内で起きた「湖東記念病院事件」を取り上げたい。私はまたもや、NHKテレビ番組「新プロジェクトX〜挑戦者たち、無罪へ声なき声を聞け・滋賀、看護助手、知られざる15年・2025年7月5日放送」に心を奪われてしまった。男性患者72歳の人工呼吸器が外されていたのはなぜか。本当に外してあったのか。ここが明確になれば事件は解決するが、地元警察や検察に焦りがうかがえる。「犯人逮捕、そして有罪にこぎつけたい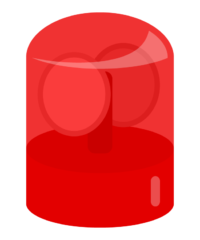 」。その使命意思が、事実を知らない病院スタッフ女性の人生を狂わせることになるとは…。恐ろしいとしかほかに言いようがない。女性は当時23歳で同僚看護師と一緒に働くが、国家試験による資格を持たない、病院が許可する看護助手という身分。女性はどういう経過をたどり、懲役12年の刑期を過ごしたのか。 」。その使命意思が、事実を知らない病院スタッフ女性の人生を狂わせることになるとは…。恐ろしいとしかほかに言いようがない。女性は当時23歳で同僚看護師と一緒に働くが、国家試験による資格を持たない、病院が許可する看護助手という身分。女性はどういう経過をたどり、懲役12年の刑期を過ごしたのか。
女性は、参考人・容疑者として検察官、刑事と向き合い、次第に誘導尋問へと操られていく。虚偽の自白がはじまる。「人工呼吸器のチューブを外し、アラーム音が鳴ってしまうから、消音スイッチを押し続けた。処遇に不満が募り、つい感情が走った結果、患者を殺した」。完璧な犯罪の清書原稿は、刑事の思惑通りに真犯人に染められた。しかし女性は、疑念を抱くことはないと、最初ははっきりと言っている。捜査はどこから元受刑者に目をつけるようになったのだろう。刑事側からみたら、 話がしやすく裏の意識がない、むしろ純粋さに惹かれていったのかもしれない。追い打ちをかけるかのように、女性もまた刑事に思いを寄せている。やりとりが出会いマッチングではないのが、もどかしい限り。なんだか、悪い運にさらさられている印象すらした。殺人容疑で逮捕状をたたきつけられる。 話がしやすく裏の意識がない、むしろ純粋さに惹かれていったのかもしれない。追い打ちをかけるかのように、女性もまた刑事に思いを寄せている。やりとりが出会いマッチングではないのが、もどかしい限り。なんだか、悪い運にさらさられている印象すらした。殺人容疑で逮捕状をたたきつけられる。
「この子に殺人など縁なきことで無罪です」。女性の両親は無実を信じ、弁護士費用の確保に懸命であった。その姿が見えたのか、地方紙支局の記者が訪ねてきた。獄中から両親にあてた350通にもなる手紙を渡され、記者は一通ずつ目を追っていく。「これが事実だとすると大変なことになる」。そう直感するもどうしてよいのか、記者個人には自問自答しか手段はなかった。それでも、取材協力に応じた両親に一言を贈る「時間をください」と…。ときが過ぎて、別の情報取得目的から本社の編集委員が支局へ訪ねてきた。「どう考えよう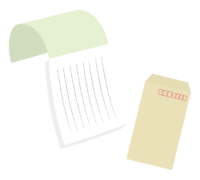 が、疑問でならない事件があるのです」。記者は思い込んでいた気持ちをデスクに投げかけた。「もう一度、しっかり手紙を読み直し迷わぬところがなければ、女性の両親の顔を見てこい」。のちに再度デスクが言う。「連載記事にするからお前が書け」。正しさを司法に問う、方法を選んだ新聞社の勇気が垣間見えた。 が、疑問でならない事件があるのです」。記者は思い込んでいた気持ちをデスクに投げかけた。「もう一度、しっかり手紙を読み直し迷わぬところがなければ、女性の両親の顔を見てこい」。のちに再度デスクが言う。「連載記事にするからお前が書け」。正しさを司法に問う、方法を選んだ新聞社の勇気が垣間見えた。
小中学時代の恩師が語る。「ごく普通の子どもではあったけれど、突然教室から抜け出す、暴れるところをみています」。そのころ、周知徹底がなされていなかった発達障害の可能性を、恩師は指摘した。支援者が増える中、獄中生活があと1年となってから、女性の精神鑑定が初めて行われる。結果 は、軽度の知的障害、発達障害、愛着障害の順で並んだ。やっと法廷でも気がつく。「防御する力が弱い」。「供述弱者」。さらに加えた。「迎合的な供述をする傾向がある」と…。人懐っこく、相手と仲よくしたい、嫌いにはしたくない。この素朴な個人の取り柄が司法の現場で、適切に理解をされなかった点は、非常に残念でならない。言い返すなら、女性のハンディキャップをうまく利用したとしても過言ではないと思う。 は、軽度の知的障害、発達障害、愛着障害の順で並んだ。やっと法廷でも気がつく。「防御する力が弱い」。「供述弱者」。さらに加えた。「迎合的な供述をする傾向がある」と…。人懐っこく、相手と仲よくしたい、嫌いにはしたくない。この素朴な個人の取り柄が司法の現場で、適切に理解をされなかった点は、非常に残念でならない。言い返すなら、女性のハンディキャップをうまく利用したとしても過言ではないと思う。
精神鑑定の結果が明らかになった時点で、事態は大きく変わっていった。ここまでの道のりでは、女性の味方に徹した人物がいる。地方の裁判官を歴任したあと、町のよろず相談を志す担当弁護士。「よほどの誤りが明確にならないと、再審請求をしてもはねられる(認められない)。それを恐れずに向かっていくのが、私の仕事です」。こんな前置きのあと話をし続けた。「途中から入っていらっしゃった新聞社のスタッフさんらと、関連情報収集、話し合いをすることで再審請求をしやすくなったのです」。と、記者との協力関係を高く評価している。ほかにこの事件の様子を知ってもらうことで、支援者同士での輪が広がっていった。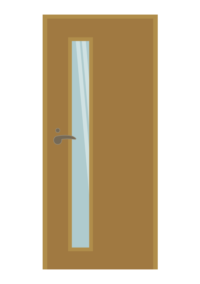 私の村でも、議会が本事件の請願書を提出した。ある議員の考えはこうだ。「えん罪をはっきりとさせるために、検察官が隠していた証拠を開示させることが決め手となっています。刑事訴訟法を改正して、証拠の開示、検察官の抗告禁止が必須となるでしょう。もしも無実の有罪があるとするなら、国家による最大の人権侵害になると考えます」。すなわち、法の見直しを求めている。みんなの支えがあって無罪への扉を開いていく。 私の村でも、議会が本事件の請願書を提出した。ある議員の考えはこうだ。「えん罪をはっきりとさせるために、検察官が隠していた証拠を開示させることが決め手となっています。刑事訴訟法を改正して、証拠の開示、検察官の抗告禁止が必須となるでしょう。もしも無実の有罪があるとするなら、国家による最大の人権侵害になると考えます」。すなわち、法の見直しを求めている。みんなの支えがあって無罪への扉を開いていく。
私にとっても障害はつきものであり、たとえ異なる障壁であろうとも、司法の現場で理解されなかった事実に腹が立った。でも、誤りはいつしか訂正が可能であると思う。そうでなければ、共生社会など言葉のみに過ぎない。女性のえん罪に発展したこの事件が、司法に対する教訓となるよう切に願う。ひいては今回のテレビ番組を視聴し、新聞記者の挑戦がとてもまぶしくて、しかも新鮮だった。警察情報担当当時に事件を知り、それからは女性の両親のもとに何度も足を踏み入れている。事件に疑いを持っての正義に満ちた行動で、娘の無実を信じる両親にとっても心強い存在となった。一方、これに背を向けるメディアがほとんどで、一人かすかな光を追う異色の取材者といってもよいだろう。つまり、1社の新聞とその記者がお互いに信頼で結ばれ ていなければ、えん罪を明らかにはできなかったに相違ない。無罪確定後、記者とともに挑んだ編集委員が振り返る。「警察からのデータをそのまま使い、女性の人生を狂わせる結果となったことに、私たち報道機関としての責任は重大です」。全国のメディアを代表しての、陳謝の説明はすごかった。 ていなければ、えん罪を明らかにはできなかったに相違ない。無罪確定後、記者とともに挑んだ編集委員が振り返る。「警察からのデータをそのまま使い、女性の人生を狂わせる結果となったことに、私たち報道機関としての責任は重大です」。全国のメディアを代表しての、陳謝の説明はすごかった。
事件が発覚してから15年。再審請求で裁判官は、自白の根拠が揺らいだとして「男性患者は自然死した可能性が高く、何者かに殺されたという事件性を認める証拠すらない」とし、加えて「あなたはうそをつく必要はありません。等身大でありままの生活を送ってください」と、説諭(せつゆ)を述べている。女性はいま両親と一緒に暮らし、疑われていた日々を忘れたい気持ちでいよう。お年寄りが好きなことから出所後、高齢者施設で働き出すが体調を崩してしまった。疑われて裁判で無実を訴える同じ境遇の人と会い、勇気づけエール を送る優しさがまたよい。そんな女性は2020年12月25日、法廷へ国家損害賠償訴訟を起こす。私のむごい体験は自分だけでもうたくさん(えん罪はごめん)。国も県もしっかり責任を負ってほしい。果たして被告はメンツを潰すことになるであろうか。女性の気持ちが真に伝わるかは、今年7月17日に分かる。 を送る優しさがまたよい。そんな女性は2020年12月25日、法廷へ国家損害賠償訴訟を起こす。私のむごい体験は自分だけでもうたくさん(えん罪はごめん)。国も県もしっかり責任を負ってほしい。果たして被告はメンツを潰すことになるであろうか。女性の気持ちが真に伝わるかは、今年7月17日に分かる。
※番組では実名で報じていますが、この原稿は女性としました。2025/07/14
|